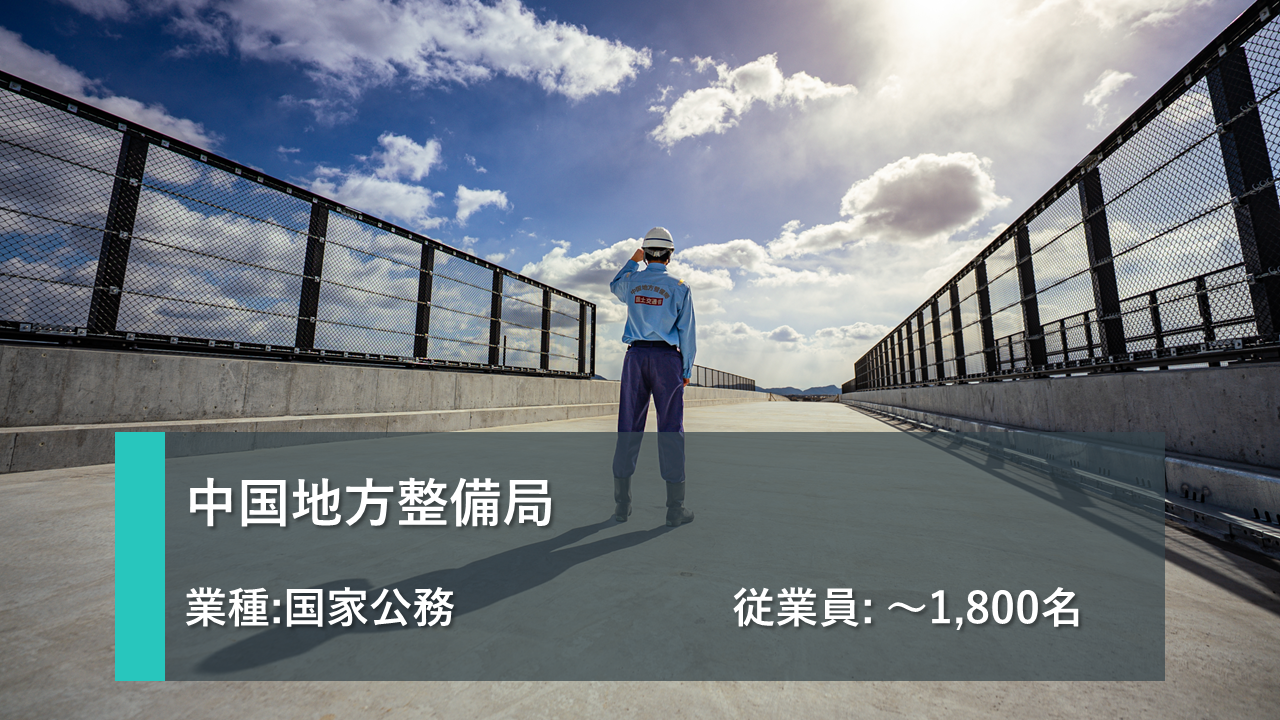S.RIDE株式会社はタクシーアプリ「S.RIDE® (エスライド)」の開発・運営を行っており、法人契約プランのS.RIDE Biz(エスライドビズ)は7か月で申し込みが1000社を突破するなど業績を急速に伸ばしている。
ソニーグループ株式会社やタクシー事業者から出向している従業員に対して、リテンション強化を目的として2024年8月よりGeppoを導入。個人サーベイと組織サーベイをどのように活用しているのか、経営管理部長の松久様にお話を伺いました。

<目次>
1. Geppoの導入背景
2. 個人サーベイの運用について
3. 組織サーベイの運用について
4. 両サーベイを実施することのメリット
5. PR・求める人材について
1.Geppoの導入背景
―――Geppoを導入いただいた背景を教えてください
松久様:Geppoの導入はリテンション強化を目的としています。
離職率自体は低いのですが、少数精鋭の会社なので、1名の離職でもインパクトが大きくなります。
そのため、1名であっても離職せずに継続的に貢献いただくための礎を作りたいということがGeppo導入の背景です。
―――Geppoのようなサーベイは複数ありますが、Geppoに決めていただいた要因はどこにありましたか
松久様:Geppoはカスタマーサクセスがついてサポートしていただけることが選定において一番大きい要素でした。
サーベイ結果が出てからの打ち手や回答の傾向から他社事例を用いながらアドバイスもいただけるので、参考にしながら進めることができます。
また、選定時は予算も重要ですが、金額感も手ごろであったため、まずはやってみようということとなりGeppoの導入を決めました。
―――個人サーベイは3問と質問数が少ないことが特徴の1つですが、それが心配になったりはしませんでしたか
松久様:導入前には心配はありました。
ただカスタマーサクセス担当から離職の3大要素がこの3つの質問でクリアになるので、ここを押さえておくことが重要といった説明を丁寧にしていただきました。
実際に運用を開始してみて、確かにこの3要素で危機察知ができるという実感もあり、今ではマネジメント層にも理解していただいています。

2.個人サーベイの運用について
―――個人サーベイの運用体制を教えてください
松久様:回答者は、ソニーグループ株式会社やタクシー事業者から出向している正社員、直接雇用の契約社員、派遣社員を含む、弊社でお仕事をしていただいているかた全員が対象となっております。
全体管理者は3名で社長、私、作業メインの1名となります。またマネジメント層は限定管理者として自身の管轄部署のみ、結果を見ることができるようにしています。
―――毎月の運用はどのように進めていただいていますか
松久様:配信日から4営業日で回答を締め切る運用をしています。
個人サーベイの構造上、追加質問を含めても最大4問なので、回答時間はおそらく1~2分でできるということもあり、配信後1営業日で概ね7割は集まります。
回答いただいていない従業員には3営業日に直接リマインドをするようにしており、その結果として回答率100%を継続しております。
締め切った後に全体管理者は全データを確認しますが、同時に、各組織のマネジメントが、ダッシュボードで自身の管轄組織のデータを見ることができ、早期の確認が実現しています。
アラートや気になるコメントがあった場合、ケースバイケースとはなりますが、担当マネジメントと対象者で15分~30分程度のショートミーティングを実施し、対応の相談を行います。
その後、担当マネジメントから対応後フィードバックを全体管理者へ共有いただき、一連の対応を完了としており、大体5~7営業日には一連の対応が完結する運用となっております。
―――従業員にはどのようにご周知いただいたのでしょうか
松久様:週2回実施している全員参加のオンラインミーティングで、「従業員皆さんのコンディションをしっかり把握し、月次で様々なことに対する意見を直接上げられるような仕組みを導入するので、回答をお願いします」とお伝えしました。
実際に回答プレビューを確認してもらい、本当に1~2分で終わるものであることを理解していただきました。
弊社は周知したらすぐに徹底できることが特徴なので、Geppoが簡単なソリューションということも相まって従業員に早く浸透したと感じています。
―――回答が集まった後、特に着目していることは何でしょうか
松久様:導入当初は単月ごとに各項目と各部署の良し悪しを見ていましたが、3、4か月続けていくとトレンドで見られるようになってきます。
トレンドの変化を部署ごとに追うようにしてから、その部署で起きている事象が捉えられるようになってきました。例えば繁忙期には仕事や健康の数値が低下しますし、繁忙期が過ぎると回復するなどの傾向が見て取れます。このため部署ごとのトレンドに着目しながら大きな変動が無いかを確認しています。
他には雨、大雨回答はもちろんですが、曇りの比率を見ていくと潜在的なリスクも見られると考えています。
―――全体管理者である社長にはどのようにGeppoを活用いただいていますか
松久様:社長は全回答を確認しており、どういったコメントが上がっているのかを確認していますので、実際の打ち手の施策立案/実行ついて議論し進める場合も、その背景を理解していますから、スピーディーに納得感を得ながら進めることができています。
実際に行った課題解決の1つのケースとして、顔を合わせる社内イベントの実施です。
弊社は各従業員が最大のアウトプットを出せる環境を自ら選定し実行する、という考え方のもと、多様な働き方をしています。基本リモートワークであり、必要に応じて出社をしています。
これには、働き方には制約があっても、働きやすい環境を作っていくことで有能なメンバーの雇用をしっかり確保していきたいという想いがあります。一方で、リモートワークの比率が高まれば対面での時間が少なくなりますから、どうしてもコミュニケーションが希薄になってしまいます。その点への懸念がGeppoのコメントにも上がってきていました。
そこで、改善策としてメンバー同士が直接コミュニケーションを図れる社内イベントを実施しました。実際に顔を合わせることで、メンバー同士がそれぞれの人となりなどの理解度を上げることができ、コミュニケーションの改善を図れた、といったポジティブなコメントをいただきました。
―――評判の良かった社内イベントについて、工夫されたことを教えてください
松久様:当日にいきなり顔を合わせるだけでなく、イベント実施前にチーム発表をして、イベントに向けて事前に準備をすることでコミュニケーションを取ってもらうことをお願いしました。そのプロセスの中でメンバー同士が少し業務から離れた状況でコミュニケーションをとることとなり、お互いにより深い理解につながったと考えています。
チーム決めについては複数の部署に跨ぎ、チームを引っ張っていただくリーダーとその補佐を中心に、なるべく普段コミュニケーションが取れていないと考えられる人をまとめる工夫もしました。
その結果、総じてポジティブな回答につながったと感じています。

3.組織サーベイの運用について
―――組織サーベイは9月に実施いただきましたが、実施前の期待感はいかがでしたか
松久様: 従業員が弊社に対してどのような期待を持っているのか、マネジメントがしっかりコントロールできているのか、を可視化したいと考えていました。
―――組織サーベイの20問については少ないとは感じませんでしたか。
松久様:個人サーベイとは違い、その心配はありませんでした。把握したいことは20問で事足りると感じており、そこから追加質問を設定することで、より踏み込んだ質問ができ点がGeppoの良いところだと思っています。
―――追加質問を設定するのに気を付けた事はありましたか。
松久様:良い部分も悪い部分もしっかり声を吸い上げるということが一番にあります。先ほど申し上げた通り、リモートワークだと雰囲気が伝わってきませんし、ノイズも入ってきません。
自分たちの見えない部分で何か起きていないか?を可視化できる質問設計に留意し、実際に追加質問から可視化できたものもありました。
―――組織サーベイの結果をご覧いただいて印象はいかがでしたか
松久様:結果として他社と比較して高い結果だったとご評価いただいたものの、個人的には、慢心することなく、まだまだ改善できる余地はあると考えています。これは他のマネジメント層も同様に感じたと思います。
ある程度想像していた範疇ではありましたが、不平不満を感じているポイントがよくわかり、しっかり手を打たないと満足度の低下につながると危機感を感じました。
―――組織サーベイを匿名にした理由を教えてください
松久様:匿名で実施した理由は回答者が言いたいことを全部表現してほしいから、という理由です。
個人サーベイは個人への対応になるので絶対に記名でないといけないですが、組織サーベイに関しては会社や組織をより良いものにしていくための種を見つけるという位置づけなので、匿名の方がいろいろな意見を言いやすいと考えました。
―――組織サーベイの打ち手についてはいかがでしょうか
松久様:打ち手はすでに打てています。結果から1か月以内にスコアを見て課題のある項目を整理し、社長を含め、全マネジメントと結果と対応策について話をしました。
例えば、去年の4月に設定したパーパス&バリューの浸透においては部署によって浸透度の違いがあることが見える化できました。それ以外にも特定の部分だけ課題がある部署もあります。できるところから打ち手を実施していきました。
―――従業員に対してはどう共有されたのでしょうか
松久様:組織の結果を共有する際に、他社と比べての乖離がある部分を提示しました。
スコアが低く不満を感じている部分があっても、それは他社と比べたら弊社はこれだけ良い結果ですよ、ということを数値を用いながらファクトとして理解してもらいました。
―――なるほど。隣の芝生よりも、実際は自分の芝生の方が青いということを理解していただいたのですね
松久様:数値でしっかりとギャップを示せるというのは非常に良いと感じています。
他社との比較はGeppoを利用している企業全体だけでなく、近い業種の結果もいただけるので、非常に参考になっています。
4.両サーベイを実施するメリット
―――両サーベイを実施するメリットを教えてください
松久様:両サーベイを併用することは必須だとと感じています。
個人サーベイは毎月実施するので設問が3問という今の軽さが従業員負担等を考えるとちょうど良いと思います。離職リスクと考えられる回答が出たときにはどれくらい早く拾うのかが重要だと思います。
一方組織サーベイに関しては組織の通知表ではないですが、もっと深く組織の強みと課題の両方を把握し、その要因を拾うことが重要と考えています。
両方実施することで、それぞれの目的に沿って実施することができています。
―――両サーベイのコメントの中であまり意見を上げない人からGeppoを通じて意見が上がったなどの発見はありましたか
松久様:それはものすごくありました。通常声が大きい人の意見が通りやすい中、声なき声を拾えるようになったというのがGeppoの大きな魅力の一つだと感じています。

5.PR・求める人材について
―――御社の求める人材について教えてください
松久様:弊社はソニーグループ株式会社やタクシー事業者から出向している社員を中心に少数精鋭で切磋琢磨している会社であり、大手企業に所属しながら、ベンチャー企業を立ち上げて運営しているのと同様の経験ができます。
自分の実力を試してみたいという気持ちを持ちつつもそのチャンスに恵まれないこともある中、弊社にはそのチャンスがあります。
まだ小さい会社なので、自身が企画や開発をした結果が営業実績や開発実績に直結し、自身の貢献で社会をどのように変革したのかというところまで見えるようになります。特に、エンジニアリング領域においては、AI/ITという武器を用いて、社会変革をリードする仕事を担えるのは魅力なのだと思います。弊社のパーパスである「革新的なモビリティサービスで心動かす移動体験を創る」に共感していただける方とぜひとも一緒に素晴らしい未来を創りたいと思っております。
―――本日は大変貴重なお話ありがとうございました