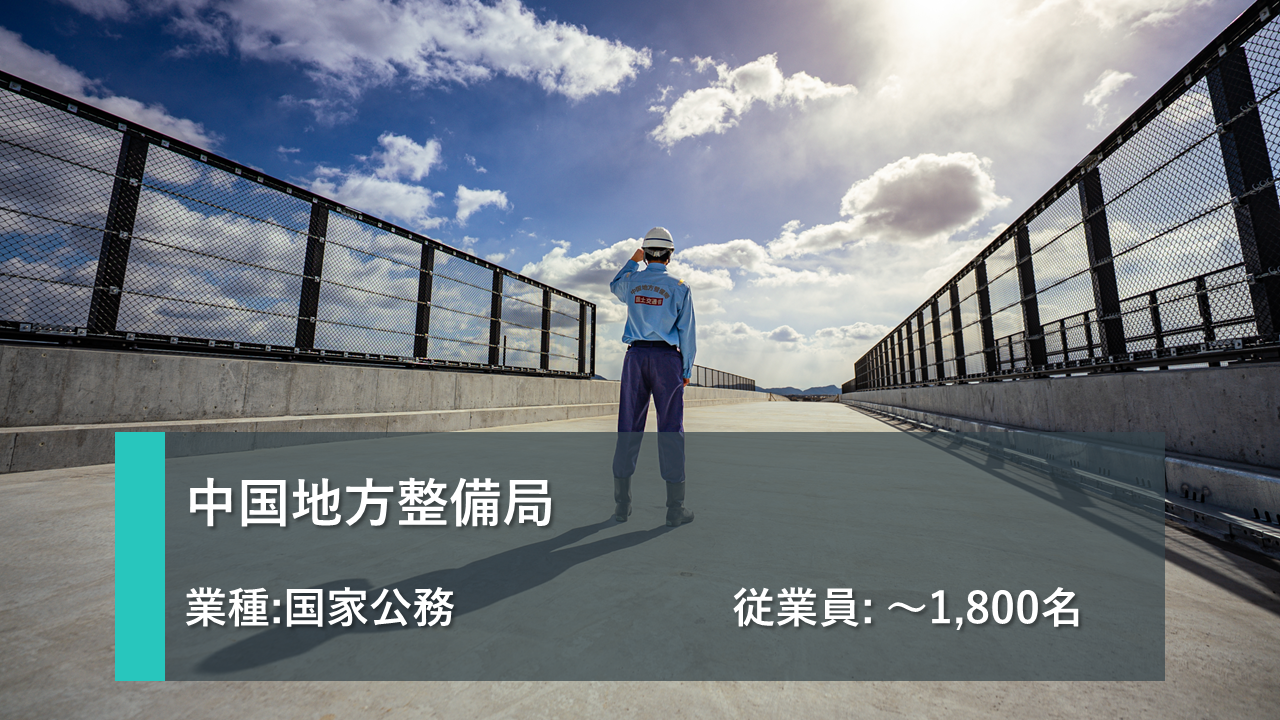株式会社ナハト様は2022年10月よりGeppoを導入し個人と組織両サーベイを並行して実施。
ベンチャーならではのスピード感ある組織変更の多さや人数が急拡大している中で、運営を担当しているO様がどのようにGeppoの運用を進めているのか、お話をお伺いしました。

<目次>
1. Geppo導入のきっかけ
2. 個人サーベイの運用について
3. 組織サーベイの運用について
4. Geppoを導入したメリット
5. PR、求める人財について

1.Geppo導入のきっかけ
―――Geppo導入のきっかけを教えてください
O様:導入のきっかけはナハト代表の安達が経営者仲間からGeppoの活用を推奨されたことです。実は過去にもGeppoを検討した時期はあったのですが、その当時の企業フェーズでは不要と判断していました。
その後、代表が勧められたということもあり、当時よりも企業規模が拡大している中で改めて検討したところ、メンバーが抱く現在の気持ちを天気マークで直感的に回答することができ、回答者の工数があまりかからない直感的なUI/UXに他社サービスと異なる魅力を感じ、導入を決めました。
―――もともとGeppoと同様のサーベイは行っていたのでしょうか
O様:Googleフォームとスプレッドシートを使って内製で実施していました。内容としてはMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)といった理念の浸透度合いや、会社や仕事をより良くするための意見・提案などGeppoでいうところの組織サーベイを自前で作り、行っていたイメージになります。
ただ、どうしても一からツールを作成し運用する工数がかかりますし、自前で実施するよりはGeppoで実施する方が、回答者がより協力的になってくれると感じました。
―――貴社として課題感はあったのでしょうか
O様:個人のコンディションに対する判断基準がないということが課題でした。
従業員数が50人〜70人くらいと少数の組織だった時は必然的に皆顔を合わせられておりコミュニケーションが取れていたので離職リスク等は個々に対応できていました。ただ、企業規模拡大によってメンバー数が増えていくなかで、今後どうしてもコミュニケーションが希薄になってしまうことが考えられ、そこに課題があると認識していました。
―――Geppoは質問数が少ないことは1つの特徴ですが、逆にそれが心配になったりしませんでしたか
O様:それは無かったです。それよりも、「大変良い・良い・普通・悪い・大変悪い」といった回答の選択肢が5つであることに懸念がありました。
というのも、人間は心理的に悩んだら真ん中の回答を選びがちになるため、5段階中のちょうど真ん中に当たる曇りの回答ばかりにならないかということを懸念していました。
―――導入時にご周知していただく際、工夫されたことは何でしょうか
O様: Geppo導入時に、回答は必須ということを全社へのチャットを活用して伝えたことは、1つ工夫した点に当たるのかなと思います。
というのも、今まで内製でやっていたものを費用かけてやるといった点や、メンバーの声をしっかりと聞き、より良い対応をしていくのであれば、全員に回答してもらいしっかりと活用していきたいという想いのもと行動できたことで、回答率100%を当たり前にできたことは一つの成功例だと思います。

2.個人サーベイの運用について
―――未回答者へのリマインドはどのようにされているのでしょうか
O様:ほとんどはアナログで追っています。メンバーへは1週間以内に回答するように伝えているので、それ以降で未回答者を確認したら、直接席まで行き、声掛けをして回答するのを見届けるようにしていました。
おかげで、今となってはみんなで回答しようという文化が社内に定着しています。
―――毎月の運用はどのように進めているのでしょうか
O様:毎月15日の配信日から毎日ログインして新規の回答がないか逐一チェックし、緊急性が高いと判断した回答があった場合、すぐにアクションを取ることにしています。
詳しくお話しすると、対応が必要と判断した回答を見つけた際、毎週金曜日を目安に私の上長に向けて、回答内容とそれに対するアクションのコメントをアラート対応履歴に入力し、まずは対応の是非を確認します。
そこから、アクションに対する上長の返答も月曜日中にはあるため、返答を受け次第すぐさまメンバーに対応を進めるといった流れで運用を進めています。主なアクションとしては、私がメンバーとしっかりと時間をとって1on1を行うことや数分程度軽めのコミュニケーションを行ったりするものや、緊急性が高く直属の部長や本部長が対応した方が根本的な解決につながると考えられるものは、回答者本人に許可を得てから本人の上長へ内容を伝え、部署に対応を任せるといったものまで幅広く行っています。
―――どのような回答に対して対応を行っていますか
O様:お天気マークでの3段階の回答も、もちろん重視していますが、ナハトの場合フリーコメントで回答された内容から対応すべきものを拾い、アクションを行うことが多いです。
―――1on1をする人や軽めのコミュニケーションをする人はどのように判断していますか
O様:天気の回答の変化、コメントの内容で判断しており、コメントの内容からは対応できるものと対応できないもので分けています。
分かりやすく架空の例を上げるとしたら、オフィスを渋谷から移転してほしい、や社内の自販機をもっと自席の近くにおいてほしい等、物理的に対応が難しい要望については、現在の状況に対してプラスに捉えられるよう1on1での伝え方を工夫しています。
反対に、緊急性の高いものでは今の業務量に対する不満や改善要望・提案、対人関係のコメントなど「改善すべきかつ、改善できるもの」を優先度高くして対応しています。
ナハトはメンバー同士が関係性の良いコミュニティを作れているという自負があるからこそ、対人関係でアラートが上がる場合は緊急度が高いと捉え、対応に取り掛かることが多いです。
―――御社の場合、対人スコアも5点満点中4点台で推移していますね。3問の設問では対人を最も重視されているのですか
O様:そうです。優先度としては1番が対人、2番が仕事、3番が健康としています。
健康に関してはナハトの現在の企業フェーズから考えて、仮にもし健康が低かったとしても、仕事の満足度が高ければ働くモチベーションが高いという印象があるので、そこまで気にはしていません。
ただ、優先度が低い回答内容だったとしても、曇りや雨で回答しているメンバーについては特に気にかけています。
―――結果のフィードバックはどのように行っていますか。
O様:前提、ナハトは社内コミュニケーションツールにChatworkを使用しているのですが、メンバーから集めた回答内容から全体に発信すべきと考えたものはChatworkで全体メンションをつけて発信しています。
経営層へのフィードバックに関してはGeppoの運用をほとんど任せていただいているので、特に行っておりません。ただ、全体のスコア自体は良く、回答内容は個人に対してのフィードバックに活用しています。
―――追加質問は毎月どのように決めているのでしょうか
O様:追加質問の設定による狙いは大きく分けて2つあります。1つ目は現状把握ができること。2つ目は意見の吸い上げができること。これができる追加質問を設定するようにしており、
その上で、私と上長でコミュニケーションを取って決めています。
例えば、賞与支給の前後や評価実施の前後、1月なら新しい年を受けての意気込みに溢れているといったその月に起こるイベントや、メンバーが抱く心象などによって大きく変わるので、タイミングをみて私から複数案を提案し2人で決定しています。
―――個人サーベイを長く活用しているとマンネリ感が課題と感じる企業もいるのですが、貴社はそういった課題は無かったでしょうか。
O様:ナハトにおいては、マンネリ感は起きていないと考えています。理由は大きく2点あります。
1つ目はGeppoの回答がメンバーにとって当たり前の存在になっていると感じるため、会社もメンバーも同じ方向を向いて活用できていることです。そこまで至ったのがここ半年から1年くらいと最近ですが、これまで浸透に向けてアクションを取り続けた結果だと感じており、意見を言いたい人がきちんと声をあげるためのツールになっているという印象があります。
2つ目はナハトならではのフリーコメントの文言にあります。
「皆さんのご意見、ご要望、ご提案がより良いナハトをつくるきっかけとなります!仕事内容や業務負荷などの仕事面だけでなく、ご自身の体調面や周囲とのコミュニケーションなど普段感じてること、何でも自由にご記入ください。」と設定しており、この文章にしてからコメントが増え、必然的にこちらからのアクションが多くなっています。
この文章には、メンバー全員で会社を作っているというニュアンスを含めたいとの想いや、みんなからの意見や要望、提案がより良いナハトを作るきっかけになるという考えからこのように設定しています。
また、Geppoの管理権限者は7名に設定しているのですが、メンバーにはその7名しか見ていないということ、困ったことがあったら気軽に相談したりGeppoにコメントしてほしいということを日々定期的に周知し回答への心理的安全性を担保し続けたことも、良い運用につながった要因なのかなと感じています。
―――自分の部下にコメントを書かれることをネガティブに感じる方がいる企業もある中で、Geppoにコメントされた内容に関して、該当メンバーの上司とコミュニケーションを取る際に気にかけていることはありますか
O様:人財対応に関しては、人事に任せていいですよという発信を心掛けています。
その発信をし続けた結果、多くの上長達に浸透したと思いますし、営業部門が収益向上に集中できる座組作りへの貢献につながった部分もあるのかなと思います。

3.組織サーベイの運用について
―――組織サーベイを3ヶ月に1回実施いただいていますが、高頻度で実施いただいている理由を教えてください
O様:最初は回答者の負担も考え、半年に1回でよいと思っていましたが、ナハトが身を置く広告業界は変化の移り変わりがかなり早い業界となるため、目まぐるしく変わる環境に心身のストレスがかかるケースもあります。
そうすると半年に1回だと手遅れになる可能性が高いと考えられるため、3ヶ月に1回というクォーターごとのタイミングが適切と判断してこの頻度で実施しています。
―――組織サーベイの打ち手の実施はいかがでしょうか。
O様:特に勤続意向に関する回答に対して打ち手を考えることを意識しています。ナハトは会社というより、1つのコミュニティとしてメンバー同士仲の良い会社なので、だからこそ働くことに関しての意識が低い回答をしている人には対応の温度感を上げ、必ず面談を実施します。
もちろんeNPSの数値やフリーコメントの内容もしっかりと見ており、eNPSの数値が前回から変化が大きい方と面談をする場合もあります。
―――スコアが高い要因はどういったところにあるのでしょうか
O様:これはエネルギッシュな20代の若い世代が多い事もあると思いますが、何か課題に直面しても引きずらず、すぐ切り替える思考を持っているメンバー多いので、3ヶ月に1回の回答の中で気持ちの切り替えができている部分があるのかなと思っています。
また、理念の浸透の面に関しても入社前のオファー面談ではナハトのMVVについて20分ほど時間を使い共感や理解していただいた上で入社いただき、入社後の研修でも同様の話をし、さらに社長とも面談を行うという3段階でナハトの理念を刻み込んでいます。さらに半年に1回行われている社内カンファレンスでも、MVVの話をするので入社後に関してもギャップは少ないと考えています。
―――2022年から組織サーベイを実施いただいていてスコアが上がっていますがどういった要因があるのでしょうか。
O様:これに関してはGeppoを介していない部分もあります。
というのも、先ほどお話ししたMVVなど会社の方針が明確に定まり、それによってメンバーの帰属意識がさらに高まったことや
最近は福利厚生といったコミュニティに属するメンバーの幸福度向上を進めるなど、メンバーと共に楽しく誇れるコミュニティを作っていけるよう様々な施策を打っています。
創業8年目のベンチャーでここまで整えられていることのすごさを理解している昔からいるメンバーのスコアは高いとは思っていますが、今後は何も整っていなかった創業期から会社が大きくなっていた過程を知らない若手から声が上がってくるのではないかと思っています。
―――組織サーベイの結果のフィードバックは全体にはされているのでしょうか
O様: Geppo管理者の7名以外は閲覧しないことを伝えているので、全体へのフィードバックは実施しておりません。
ただ、良いこともそうじゃないことも、会社として発信した方がよいケースについてはGeppoの結果を受けてということは伝えず、私からの社内広報としてチャットワークで全体の場へ発信することが多いです。 
4.Geppoを導入したメリット
―――Geppoの運用に関する負担度合いとしてはいかがでしょうか
O様:Geppoの内容を踏まえた上での個人への面談は大体月10人~15人ほどおり、1人につき30分実施しているので約8時間弱、面談内容の登録作業で1~2時間、打ち手を考えるための分析で2時間ほどなので毎月12~3時間かけています。
ただ、メンバーのエンゲージメントや幸福度に直結する行動であるため、まったく負荷に感じたことはありません。
―――Geppoを導入いただいたメリットについてどう感じていますか
O様:前提、私の役割はハピネス担当と言って、メンバーのエンゲージメントや幸福度の向上を目的に従業員の課題発見や解決、マインド低下の改善をする役割なので、Geppoというツールを命と思っているほどありがたく感じています。
そのため、Geppoの活用は従業員を深く知ることができ、プラスのことでもマイナスのことでも最終的にこちらの対応によってすべてが良い方向につながると考えているので、組織のために活用できているという実感があります。
メンバーの中には、直属の上司や仲間には時には言いにくいけれど、Geppoであれば伝えることができる、伝えたことでスピーディにアクションをしてくれる、という安心を感じてくれているメンバーもいます。
―――ハピネス担当というのは考えも含めてとてもO様にぴったりですね!
O様:私自身ポジティブな性格というのもあり、私の上長が名付けました。(笑)
逆にハピネス担当なので、私自身がハピネスな状態でなかったらまずいと。
仮に私の気持ちが沈んだまま1on1をしてしまうと、従業員へも伝わってしまうのかなと思うので、そうならないように日々仕事することを心掛けていますね。

5.PR・求める人財について
―――先ほどナハトで働く人物像についての話がありましたが、どういった人財が貴社に合うと考えていますか
いわゆる地頭がよくてガッツがあって、イケてる素直な人が当てはまります。特にイケてるという言葉に内包される要素が多いんですが、見た目の問題ではなくて自然と人が集まってくる人間性のことを指します。
地頭に関しては、マーケティングの仕事においてはそもそもロジックで人の心を動かすことは必要なので求めますし、ガッツというのはベンチャー特有の変化に負けない気持ちの強さ。そこに素直さが加われば満点という感じです。ぜひそういった方と働けたらなと考えています。.png?width=726&height=726&name=%E6%A8%AA%E3%83%AD%E3%82%B4_%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC(RGB).png)
―――本日は大変貴重なお話ありがとうございました