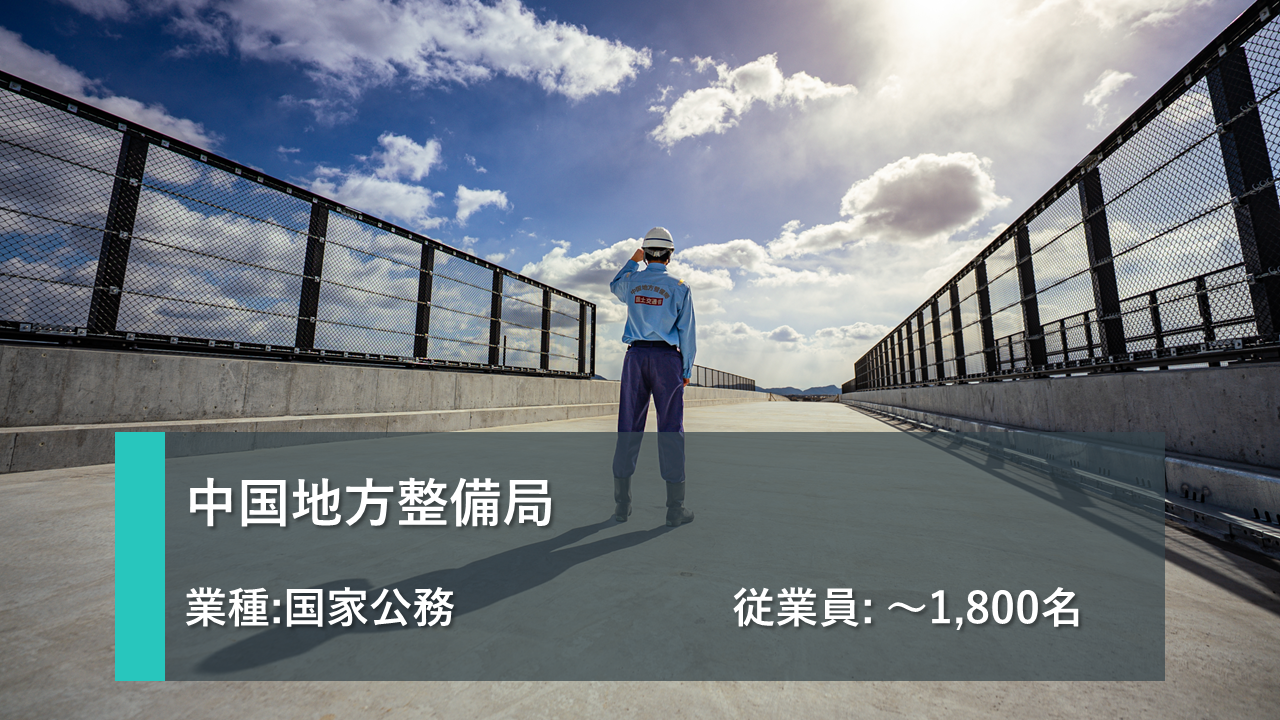2024年10月より全職員1,800名を対象にGeppoを導入。個人サーベイと組織サーベイを実施し、回答率約90%前後を維持しながら個人サーベイは現場主体、組織サーベイは事務局主体と目的を分けた運用の意図などについて中国地方整備局厚生課長の次郎丸様にお話を伺いました。

1. Geppo導入のきっかけ
2. 個人サーベイの運用について
3. 組織サーベイの運用について
4. 両サーベイを実施することのメリット
5. PR・求める人材について
1.Geppo導入のきっかけ
―――Geppo導入のきっかけを教えてください。
次郎丸様:2023年当時の部長がパルスサーベイに関する記事を読んだことがきっかけでした。
メンタル不調者や若手層での離職が気になっていたタイミングでしたので、何か良い打つ手はないかと思案していたところ、同記事が目にとまり、職員のコンディションを可視化できるなら対策できるのではないかということで、2024年2月にトライアルとして1部署で導入しました。トライアルで良い感触が得られたので、2024年10月より全職員1,800名を対象に本導入しました。
―――本導入にあたって、どのようなことを検討いただいたのでしょうか。
次郎丸様:全職員に対して導入すべきか、あるいは入社何年目まで、離職リスクが高いと考えられる世代、特定の組織等といった対象者に対して実施すべきか議論しました。
しかし転職やメンタル不調は特定の層に限るものではないため、全職員に対して行う方が効果的だと判断しました。
実際に使ってみて、回答者側としては簡単に答えられること、管理者側としては、集計結果が見やすく、機能面で使いやすいと感じました。
―――職員の皆さまにはどのようにご周知いただきましたか。
次郎丸様:「強制ではないこと」、「(パルスサーベイ導入前に実施していた)ストレスチェックとの違い」、「3問の質問に天気マークで直感的に答えられるため率直に回答してほしいこと」を伝えるようにしました。
各組織の幹部にGeppoを行うことを周知した上で、各幹部から所属単位のミーティングで周知してもらいました。それとは別で全職員にメールでの案内も行っています。
メールの内容としては、パルスサーベイやGeppoについての説明と、Geppoから届くメールは開いてもセキュリティ上問題ないことを伝えました。
2.個人サーベイの運用について
―――1,800名の回答者に対して管理者権限はどのように設定し、運用されていますか。
次郎丸様:私たちの職場には23の事務所があるのですが、事務所においては、所長や副所長を限定管理者として設定し、限定管理者から各職員に対して対応いただいています。
事務局から限定管理者に対しては、アラート発生者や気になるコメントを記入している職員に対してメール等で状況をヒアリングしてほしいということ、特に気になる職員に対しては面談を実施してほしいというお願いをしていて、アラート対応履歴の入力が無い場合は催促を行っています。
毎月15日配信なので、できれば回答後すぐに対応してもらいたいと考えていますが、併せて丁寧でしっかりとした対応も求められるため、遅くとも月が替わったタイミングまでには各限定管理者に対応、および履歴の入力をお願いしています。
基本的に限定管理者が対応していますが、対応に迷うことがあれば事務局に相談して、双方で話をしながら対応方針を決めています。
―――個人サーベイの運用で不調の発見等につながったケースを教えてください。
次郎丸様:1問目の質問(仕事に対する満足度はいかがですか?)では業務量や仕事へのモチベーションについての発見、2問目の質問(あなたの職場の人間関係は良好ですか?)では、雨の回答があった場合、所属組織内で上司や同僚とのコミュニケーションが不足、3問目の質問(最近、よく眠れていますか?)からは、体調面に関することが確認でき、面談のきっかけになっています。面談を通じて翌月の結果が良くなったケースは多く見られます。
5段階の天気マークで直感的に回答ができるので、自身の状態が素直に反映され、普段のコミュニケーションでは気付きにくかった不調や変化を発見でき、しかもそこからリアルタイムな対応につなげられるのがこのパルスサーベイの良いところだと感じています。
少し話が逸れますが、不調でない者のフォローという側面にも目を向けていて、回答をお願いしている職員全員に対して、回答率や面談後の回復率などをフィードバックしてサーベイの意義を発信し続けています。
―――3問の質問が少なすぎると心配はなかったでしょうか。
次郎丸様:質問数が多ければ多いほど詳細は分かりますが、答えやすさを優先し直感的に答えられる仕組みになっている方が毎月実施するサーベイにおいては良いと考えました。
Geppoは20問の組織サーベイもあり、毎月のコンディションチェックとすみ分けができるので心配はありませんでした。

3.組織サーベイの運用について
―――組織サーベイを25年1月に実施いただきましたが、どのような気づきがありましたか。
次郎丸様:局全体や事務所など組織毎、年齢等別の現状が把握できたことです。良い部分も課題がある部分もそれぞれ把握することができたのが大きいと感じています。
―――結果報告についてはいかがでしょうか。
次郎丸様:幹部に報告しました。どういった取り組みができているからスコアが高く職員の満足度が高いのか、逆にどういったことが足りないから満足度が低いのかを共有し認識してもらうことで、今後どのような対応を行っていくべきなのか検討を進めることができました。
例えば、電子化が遅れている、といった声には、AI活用や執務環境改善に係る予算要求なども進んでおり、実際にアクションが前に進んでいる感覚があります。
―――限定管理者には共有されたのでしょうか。
次郎丸様:限定管理者には共有していません。
組織サーベイの内容は私たちの場合各事業所単位でできることが少ないと判断したため、まずは幹部や本局の人事や予算に関わる部署に共有しました。
4.両サーベイを実施することのメリット
―――両サーベイを実施することのメリットを教えてください。
次郎丸様:個人サーベイは各組織の限定管理者が主体となり、毎月実施することで変化を追いながら対応を進めることができます。また、コメント欄には、例えば業務の進捗が順調で明るい職員から「業務上の悩み」が記載されるケースなど、業務運営上貴重な情報となっています。さらに、コメント欄の記載から、職員のメンタル状況が早期・定期的に把握できることを期待しており、職員が対話以外に声を届けられる大切なツールになっていると考えます。
組織サーベイは事務局主体としてすみわけ、弊局全体としての課題に対する施策の実施を検討することができます。
組織サーベイはまだ1回しか実施しておらず効果測定ができていないので、2回目以降の結果をみながら引き続き施策の実施につなげていきたいと考えています。

5.PR・求める人材について
―――Geppoを今後どのように活用していきたいですか。
次郎丸様:職員にかなり浸透してきているのは肌で感じていて、率直に回答いただいていると思います。また、幹部層にも月次報告を始めたことでかなり関心を持ってもらえています。
今後継続運用していく際のポイントとしては現場での対応の質を向上していくことだと考えており、限定管理者に対してアラート発生者への対応の仕方や全体の傾向を共有する「お悩み相談会」を定期開催していきたいと考えています。
国民の皆さまからお預かりした税金を使って運用させていただいている事をしっかりと意識し、職員とコミュニケーションを取ることで働く環境を良くし、もって地域貢献に還元していきたいと考えています。
―――貴局の求める人材を教えてください。
次郎丸様:中国地方整備局のミッションは、中国地方の安全、安心、豊かな地域社会を支えることです。
道路や河川、港湾、住宅まちづくりといった社会資本整備を通じて防災・減災や地域の活性化に取り組んでいます。
そのため職員には幅広い分野への興味関心、それから広い視野、高いプロ意識をもって職務に当たることが求められます。これはひとえに中国地方を良くしたいという強い志を持った方が最適な職場であると考えています。
仕事は一人ではなく、チームで行うものです。何事にも意欲と熱意を持って取り組むことに加えて、チームワークとコミュニケーションを大切にし、その上で先ほどもお伝えした地域貢献への意識を持つ、そのような人材を私たちは求めています。

―――本日は貴重なお話ありがとうございました。