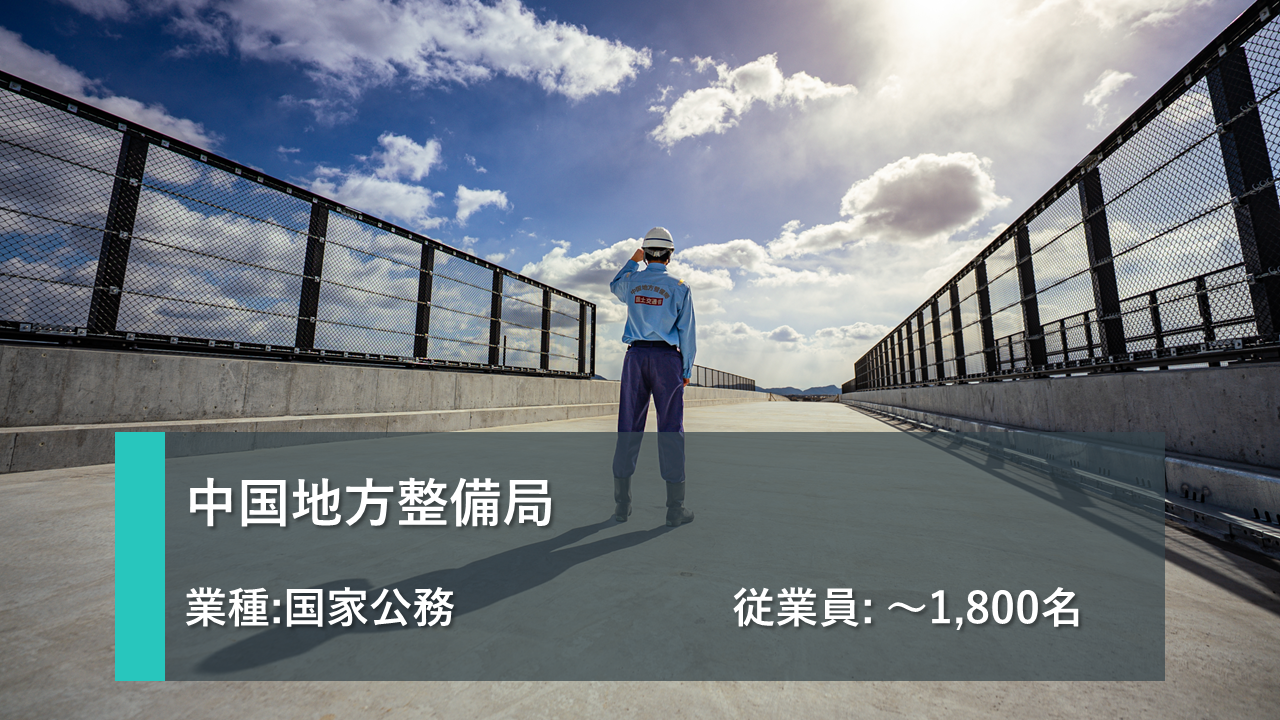株式会社プロジェクトホールディングス様は、2024年2月よりGeppoを導入し、個人・組織両サーベイを同時に実施。ベンチャー特有の従業員数の拡大から状況把握がしにくくなってきたという課題感に対して、両サーベイを活用しどのような運用を進めたのか、人事ユニット ユニット長の柳谷様にお話を伺いました。

<目次>
1. Geppoの導入背景
2. 個人サーベイの運用について
3. 組織サーベイの運用について
4. 両サーベイを実施することのメリット
5. PR・求める人材について
1.Geppoの導入背景
―――Geppoを導入いただいた背景を教えてください。
柳谷様:新入社員の採用を進め人数が増えていくなかで一人ひとりの考えていることが把握しにくくなってきていました。
退職者が出たときに個別にヒアリングをするのですが、退職に至るまで感じていたことを誰も把握できておらず、本人の中で一人でいろいろと考えて退職を決断してしまっていることが多かったのです。
そのため、従業員の声を聞きコンディションを把握していきたいという目的から導入しました。
―――元々コミュニケーションはあまり多くなかったということなのでしょうか。
柳谷様:導入当時は、業績を伸ばすためのコミュニケーションを優先しており、個人のコンディションや今後のキャリアといったコミュニケーションは後回しになっている実態が一部あったと感じます。
―――Geppoに決めていただいた要因はどこにあったのでしょうか。
柳谷様:当時リクルートでGeppoを利用していたメンバーがおり、回答の負荷が低くそれでいて正直に回答してくれる従業員が多かったためおすすめいただきました。
―――個人サーベイは3問と少ない設問数ですが、そこに心配はなかったでしょうか。
柳谷様:コンディション把握においてはタイミングキャッチが重要と考えており、頻度は最低でも月1回が必要。その場合、設問数が多いと回答者への負担が大きいと感じます。私も以前Geppoを管理者として利用していたこともあり、そこのバランスがいいと感じていました。
―――導入に至る壁は特になかった印象でしょうか。
柳谷様:そうですね。元々の課題から、まずはよさそうなツールを入れてみようといった、ベンチャーならではのスピード感をもって導入を進めることができました。

2.個人サーベイの運用について
―――配信対象範囲と管理者を教えてください。
柳谷様:弊社主要子会社とホールディングス組織を対象としています。対象人数は約160名でその内全体管理者は人事メンバーの5名となります。
―――従業員への周知はどのように行いましたか。
柳谷様:取り組みが始まる前は実施目的と毎月回答してほしい旨をSlackで全体に発信するチャンネルで行いました。
以降は新しく回答対象となる従業員に対しては周知を行っていますが全体に対しては特にしていません。
―――毎月の運用サイクルを教えてください。
柳谷様:月初に配信がスタートし、都度ログインして回答率のチェックを行います。2週間くらいで回答率85%くらいになりますが、そこから95%は超えるようにしたいと考えているので未回答者に個別プッシュしています。
それと並行して、アラート者や気になるコメントには随時対応を行うようにしており、管理者5名の内、私含めた3名がメインでアクションを行っております。
アクションについては、アラートの内容や過去の接点などをもとに、人事内で対応者を決めて進めています。残りの2名はGeppo以外で従業員とかかわることもあるので、その際にGeppoの履歴を確認した上でコミュニケーションを取ることもあります。
―――メインの3名はGeppoに1か月でどれくらい時間をかけていただいていますか。
柳谷様:3人で大体10時間くらいかと思います。
回答チェックはそこまで時間がかからないので2週間で1時間くらい、面談についてはだいたい月10名くらい30分ずつ、その後の対応等含めてそれぐらいになります。
今くらいのアラート数であれば現状の分担で無理なく運用できています。
―――フィードバックはどのようにしていますか。
柳谷様:役員向けと従業員向けに行っています。
まず役員向けにはExcelで集計したものにて報告を行っています。もちろん個人が特定されない形で行っており、主に全体の傾向や組織別、役職別の内容になります。スコアも比較的安定しており、月次でスコア低下する部分についてはプロジェクトの繁忙など単発のものが多いので、過去3か月程度のスコアを継続的に見て異変がないか確認するような感じで報告しています。
従業員向けには2か月に1回程度フィードバックを行っています。
回答率とアラート率、3問の全体平均、追加質問でシェアした方がよいもの、いただいた組織要望に対する対応状況をフィードバックしています。それに対して従業員から反応をいただけることもあるので、見てくれているんだなと感じています。
―――追加質問の内容はどのように決めているのでしょうか。
柳谷様:人事の中で持ち寄って、その中から相談して決めるようにしています。人事評価プロセスがきちんと回っているか確認したり、新たに検討しているインナーコミュニケーションの施策についての感触を問う質問を設定したりと、人事が従業員の生の声を集めたいケースで活用しています。率直に回答してくれるので使い勝手がよく、気に入って使っている機能です。
―――面談を行って以降、好意的な事例はありましたか。
柳谷様:アラートは、誰に相談していいかわからない、悩んで出口がないことを吐露してアドバイスをもらいたいという内容も多いので、話を聞いたことで本人がスッキリして「気持ちを変えてやってみようと思います」という前向きな発言をもらったりします。また現場ラインを巻き込む必要があるものは、本人と相談の上で現場ラインに繋いで対応を進め、早期解決を目指します。
いずれの場合も、対応により翌月アラートが解消できた際には手ごたえを感じますし、そういったことから、Geppoを通じて課題として上げた、従業員の声を拾っていくことはできているという実感を持てています。

3.組織サーベイの運用について
―――組織サーベイは24年2月と8月、25年2月と3回実施いただいています。こちらはどのような目的で実施いただきましたか。
柳谷様:会社としてエンゲージメントを指標において測っていきたいと思っていたので、それをGeppoで出来るということで活用させていただいています。
―――20問の固定質問については一般的な組織診断ツールの中では少ない設問数ですが、こちらに心配はなかったでしょうか。
柳谷様:必要な内容に絞られているので、心配はありませんでした。そこから追加質問も最大30問設定することができるので、独自に聞きたいことについても網羅できると考えております。
―――3回実施いただいていてeNPS含めて全体のスコアが良くなっていますが、どのような施策を実施されたのでしょうか
柳谷様:初回実施時は、組織改革もスタートしたばかりでした。
組織の体制を大きく変えたり、中途採用を強化し、シニア層に新規参画していただいたりと改革を進めた結果、2回目のスコア改善の手ごたえを感じました。
3回目も同様、2回目のスコアから施策を検討し実施してきたことでより良いスコアになったので、打ち手がきちんと浸透し効果的だったということがわかりうれしく感じています。
―――具体的にどのような打ち手を実施したのでしょうか
柳谷様:コンサルによくあるフラットな組織体制を、ラインを強化し育成を重視したい考えからピラミッド構造の組織に変更しました。また、業績と個人の成長を両立するという方針のもと、人事評価制度も変更しました。
他には、事業戦略の浸透と同僚の称賛の項目が同業他社と比べて唯一低く出ていたのでインナーコミュニケーションへの課題を感じ打ち手をとっていきました。
戦略の浸透については今までは社長が全体に話して終わりになっていたところを、各組織階層に対して順次ブレイクダウンをしていき、きちんと組織の戦略に紐づいて説明することを強化しました。同僚の賞賛については組織階層をピラミッド構造にしたことによって横の組織のことが分かりにくくなってしまったため、月に1度社内報で各組織のGood topicを紹介するようなコンテンツを追加しました。
―――打ち手を検討する際にはどういったことを注意されましたか。
柳谷様:費用対効果は非常に気にしていて、極力負荷やコストをかけずに本質的な効果を出していけるようにするということを意識していました。また追加施策を行う場合、特に運用主体者には、背景や意図を合わせて伝えることで実施する意義を理解してもらうように努めています。
―――こちらもフィードバックはどのようにしたのでしょうか。
柳谷様:役員には、役員会のアジェンダの1つとして報告場所を設け、全体の結果を共有しながら人事として感じている課題感とそれに対する打ち手、役員にも行っていただきたいことを報告と承認をいただくようにしました。
従業員に対しても承認いただいた内容を含めて役員に報告したことと同じ内容をフィードバックしました。
スコアはそのままフィードバックし、ほとんどGeppoから提供いただいたレポートをそのまま使用しています。
4.両サーベイを実施するメリット
―――個人サーベイと組織サーベイを併用することでメリットに感じた事を教えてください。
柳谷様:個人サーベイは一人一人のコンディション把握、組織サーベイは会社全体の傾向や組織別の傾向が見えるので、それぞれに対してどこに打ち手を進めていくのかが明確になります。
いずれも「従業員がベストパフォーマンスで働き続けられる環境」を作ることに目的がありますが、個人サーベイは毎月の足元のコンディション変化を追うこと、組織サーベイはやや長期的な視点で、エンゲージメントや勤続意向を把握することを意識して、対応を行っています。
勤続意向を低く回答している方に対しては、ある意味第三者的な人事の立ち位置から、フラットに回答の背景をヒアリングしています。弊社の傾向ですが、コンサル業界かつ若い人が多いので、ずっとこの会社に居続けるという感覚がそもそもない人も多いです。そういった場合はキャリア志向性のヒアリングに切り替えて、会社としてキャリアの幅をどう広げていくのかというテーマの貴重な一次情報として取り扱っています。

5.PR・求める人材について
―――貴社の求める人材を教えてください
柳谷様:弊社の強みは、組織支援型の役割で参画する案件が多く、日々、顧客企業の部課長クラスとの接点を持ちながら業務を進めている点にあります。プロジェクト型の案件においても、若手であっても一部のタスクのみに閉じて関与することは少なく、常に顧客課題の本質に近い場所で仕事ができるのが特徴です。
単に依頼された業務をこなすだけでなく、顧客の課題にマッチした解決策を提案することができ、その提案をもとに新たなサービスとして事業化していくような、事業開発にも関わるチャンスがあります。
このように、若手のうちから数多くの打席に立つことができるため、実践を通じて大きく成長できる環境が整っています。自ら機会をつかみ、挑戦しながら成長していきたいという意欲のある方には、非常にマッチした職場です。
―――本日は大変貴重なお話ありがとうございました