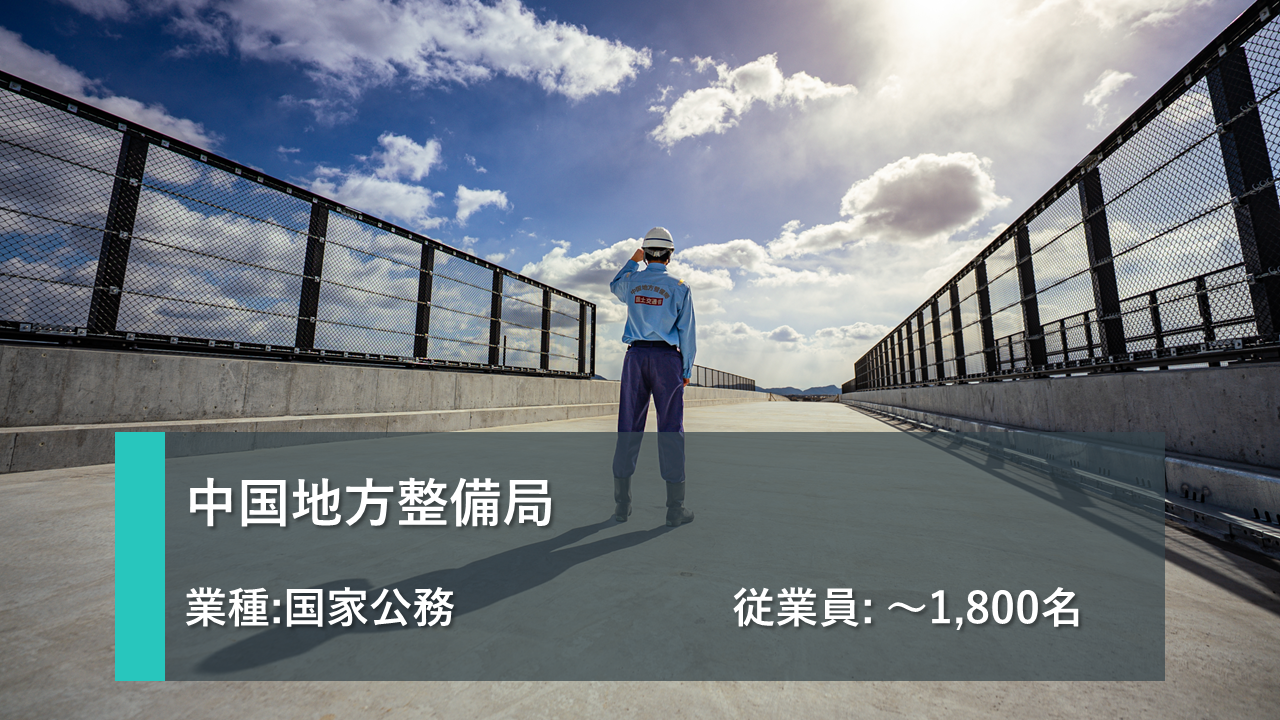人事の重要な業務の1つに「人事評価」があります。社員を評価する際には、売上や利益のような業績評価だけでなく、個人の役割やスキルなども加味して判断しなくてはなりません。
しかし人事評価を通じて「社員をどのように評価したら良いのか」「現状の人事評価をより公平なものにしたい」といった悩みを抱えている企業も少なくありません。本記事では、人事評価基準の概要から評価項目の考え方、人事評価基準を導入する方法やポイントについて詳しく解説します。
目次
- 人事評価基準とは
人事考課との違い - 人事評価基準を定める必要性
人事評価による処遇の根拠や公平性を示す
社員のマネジメントや育成に活用する
企業文化や重視する価値観を醸成・浸透させる - 人事評価基準の代表的な3つの項目
実績を評価する「業績評価」
能力を評価する「スキル評価」
勤務態度を評価する「情意評価」 - 人事評価基準の具体的な項目
業績評価の具体的な項目
目標達成率
達成予算額
KPI達成率
能力評価の具体的な項目
問題解決能力
コミュニケーション能力
マネジメント能力
専門的技能
知識
情意評価の具体的な項目
協調性
積極性
責任感 - 人事評価基準を作る6ステップ
1.経営戦略や人事戦略から目的を明確にする
2.人事評価の項目を決める
3.各評価項目ごとの評価基準(段階)や方法を設定する
4.評価者の選定をおこなう
5.評価のフィードバックやレビュー方法を定める
6.評価結果の振り返りや活用について定める - 人事評価の主な評価手法
MBO(目標管理制度)
OKR評価
360度フィードバック
コンピテンシー評価 - 人事評価基準を決める際の注意点
評価基準は複数のメンバーやチームで策定する
職種ごとに定量目標と定性目標の基準を明確にする
評価者への研修を実施する
定期的に評価基準を見直す - 人事評価基準の定期的な見直しにサーベイツール「Geppo」が有効
- まとめ
人事評価基準とは

人事評価基準とは、組織やチーム、個人の業務パフォーマンスや行動を評価する基準のことを指します。人事評価は、社員の能力や成果を適正に評価して、人事施策に反映させることが目的となり、企業が事業の目標を達成するためにもに欠かせない基準です。
人事考課との違い
人事評価と人事考課は、どちらも社員の業務パフォーマンスや行動を評価する点で共通していますが、それぞれの目的は大きく異なります。
人事評価は社員の強みや弱みを把握して、結果をフィードバックすることで社員の育成やスキルアップを促すのを目的としています。一方で人事考課は、社員の成果や能力を評価して、給与や昇進、人材の配置などの人事施策に反映させるのが目的です。
人事評価基準と人事考課は混合して考えるのではなく、それぞれの目的の違いについて正しく理解しておきましょう。
人事評価基準を定める必要性

人事評価基準を定めずにいると、評価する人によって評価にばらつきが出てしまう可能性があります。また社員は評価に納得しにくく、不満を抱くかもしれません。
ここでは人事評価基準を定める必要性について解説します。
人事評価による処遇の根拠や公平性を示す
人事評価の結果は、社員の給料や昇給、昇格といった処遇に反映されるのが一般的です。社員の給料や昇給への基準、昇格の基準を明確にすることで処遇の根拠を全社員に提示でき、公平性を保てます。
一方で人事評価基準が明確になっていないと、処遇に対して社員が不公平感を抱いてしまいやすく、モチベーションの低下や離職に繋がってしまう可能性があります。
社員のマネジメントや育成に活用する
人事評価の内容を社員に対して、適切なフィードバックをおこなうことで社員はどの業務に対して評価されて、どこに課題があるのかを理解しやすくなります。
自身の強みや弱みを把握して改善できれば、昇給や昇格などの評価が得られるためモチベーションの向上にもつながり、成長できるでしょう。
企業文化や重視する価値観を醸成・浸透させる
人事評価基準は、企業がどのような方針や価値観を持っているのか、社員にどのような行動を期待しているかといったような企業の考え方が反映されます。
そのため、人事評価基準を構築すると「企業が何を重視していて、どのような社員の働き方を求めているか」を社員に対して周知できる側面もあります。
人事評価基準の代表的な3つの項目
人事評価基準は大きく3つの評価項目で構成されるのが一般的です。どの評価も社員のモチベーション向上、組織の成長に欠かせない要素です。
人事評価がどのような項目で構成されているのか、具体的に解説します。
実績を評価する「業績評価」
業績評価は、社員が達成した成果や結果を評価するもので、売上や利益、顧客満足度、目標達成度などが対象になります。業績評価は、企業の目標や経営戦略の達成に直接的に貢献した社員を評価するために重要です。また、社員のモチベーションや意欲を高める効果もあります。
能力を評価する「スキル評価」
スキル評価は、社員が持つ知識やスキル、資格などを評価します。専門知識、コミュニケーション能力、リーダーシップ、問題解決能力などが評価の対象になります。
スキル評価は、社員の成長やキャリア開発を促すためにとても重要な要素で、さらに業務の効率化や品質向上にもつながります。
勤務態度を評価する「情意評価」
情意評価は、社員の勤務態度や人間性を評価します。勤務時間の遵守、コミュニケーション能力、協調性、コンプライアンス意識などが評価の対象となります。
情意評価は、企業の風土や文化を醸成するために必要で、また社員同士の協力やチームワークの向上にもつながります。
人事評価基準の具体的な項目
人事評価基準の代表的な3つの要素を基準に落とし込む際には、より細かな項目として設定する必要があります。
ここからは「業績評価」「能力評価」「情意評価」の3つについて、より細分化し、それぞれの具体的な項目とその評価の仕方について解説します。
業績評価の具体的な項目
定量的な数字に基づく業績評価の具体的な項目について、目標達成率、達成予算額、KPI達成率の3つに分けて解説します。
目標達成率
目標達成率は、社員が設定した目標をどの程度達成できたかを評価する項目です。
目標達成率を評価する際、目標の難易度や達成状況を踏まえて、適切な評価基準を設定する必要があります。目標達成率が100%に届かなかった場合でも、設定していた目標の難易度が高かったにもかかわらず、極端に低い評価をつけてしまうと、社員の不満につながりかねないため注意が必要です。
達成予算額
達成予算額は、社員が担当した案件やプロジェクトで、達成した予算額を評価する項目です。定量的な指標になるので、客観的に評価しやすいというメリットがあります。
ただし、企業の業績や市場環境などによって影響を受けるため、単独で評価するのではなく、他の評価項目と組み合わせて評価することが重要です。
KPI達成率
KPI達成率は、社員が達成すべき重要な成果指標(KPI)をどの程度達成できたかを評価する項目です。KPIは、企業や職種によって設定はさまざまですが、営業職であれば、売上高、顧客単価、新規顧客獲得数などがKPIとして設定されるケースが多いです。
KPI達成率を評価する際には、KPIの重要度や達成状況を踏まえて、適切な評価基準を設定しましょう。また、KPIの達成率だけでなく、KPIを達成するために社員がどのような行動をしたかなども評価するのも重要です。
社員の等級や職種に応じて、定量的な目標、定性的な目標を設け、適切な評価をおこなう体制にするといいでしょう。
能力評価の具体的な項目
能力評価の具体的な項目としては以下が挙げられます。
問題解決能力
問題解決能力とは、問題を的確に把握して解決策を立案・実行する能力のことを指します。
「問題をどのように把握しているのか」「解決策をどのように立案しているのか」「どのような解決案を実行しているのか」について判断しましょう。
コミュニケーション能力
コミュニケーション能力は、対人や組織を円滑に進めるために必要とされる能力を指します。
「相手とのコミュニケーションをどのように取っているか」「相手に理解してもらうためにどのような工夫をしているのか」「相手との関係をどのように構築しているのか」の視点で判断しましょう。
マネジメント能力
マネジメント能力は、人や組織を管理・運営するための能力で、管理職や主任レベルで必要となるスキルです。
「部下やメンバーをどのように管理しているのか」「チームや組織をどのように運営しているのか」「組織のパフォーマンスを上げるためにどんな取り組みをしてるのか」の視点で評価しましょう。
専門的技能
専門的技能とは、特定の分野に関する理解や知見、技術のことです。
専門性の高い業務に必要不可欠なスキルになります。
「スキルを取得するためにどのような努力をしているのか」「業務で活用できているのか」「スキルをより向上させるための取り組みは何なのか」について評価しましょう。
知識
知識も専門的技能と同様、業務をスムーズにおこなうために重要な能力です。
知識を評価するときは、「業務に必要な知識をどの程度習得しているのか」「知識を業務にどのように活用しているか」について評価しましょう。
情意評価の具体的な項目
情意評価の具体的な項目は以下の通りです。
比較的、抽象度の高くなりやすい項目でもあるため、きちんと精査しながら基準を策定していく必要があります。
協調性
協調性は、周囲の人と協力して物事を進める能力のことを指します。チームや組織で進める業務を円滑にするために欠かせません。
「チームではどのような役割を担っているのか」「チームのメンバーと良好な関係を築けているのか」などを基準に評価しましょう。
積極性
積極性とは、自発的に行動して目標を達成するために努力する姿勢のことです。
「目標達成のためにどのような努力をしているのか」「新しいことに取り組んでいるか」「周囲を巻き込んで行動しているか」について評価しましょう。
責任感
責任感とは、自分の行動や結果に責任をもつ姿勢です。人やチームからの信頼を得るために重要な能力になります。
「自分のミスや失敗を素直に認めて、責任を取っているか」「自分の業務に責任をもって取り組んでいるか」について評価をおこなうことが重要です。
人事評価基準を作る6ステップ
人事評価基準を作成する際は、適切な手順で進めると良いでしょう。
あらかじめ手順を知っておくと失敗する可能性が低く、スムーズに導入できます。
1.経営戦略や人事戦略から目的を明確にする
まず、人事評価を導入するにあたって目的を明確にします。
目的を明確にする理由は、社員に「人事評価制度が何のためにあるのか」「社員をどのように成長させていきたいのか」について理解してもらうためです。
会社の評価基準として、どのような人材や働きぶりを評価するという目的を明確に伝えることができれば、社員も向かうべき方向性をイメージしやすくなります。企業の経営理念やビジョン、ミッションやコアバリューなどをもとに考案すると良いでしょう。
たとえば、企業理念が「人々の暮らしを豊かにする」であれば、人事評価の目的は「顧客満足度を向上させる社員を評価する」などを設定します。目的を明確にする際は、経営戦略や人事戦略の指針を参考にするれば、効果的な制度を設計できます。
2.人事評価の項目を決める
目的を明確にしたら、次に具体的な人事の評価項目を決めていきます。
3つの評価項目(業績、能力、情意)をベースに、さらに細かく評価項目を作成していきましょう。
たとえば、能力評価であればコミュニケーション能力などが挙げられます。業績であれば、KGI達成やKPI達成などが該当します。
人事の評価項目についても、経営計画を達成するために設計する内容となるので、こちらも企業理念やビジョンと照らし合わせておこなうことが重要です。
3.各評価項目ごとの評価基準(段階)や方法を設定する
次に、決定した評価項目に対して評価点を設けて、何段階でどのような評価を判断するのかを決めます。報酬制度や階層、階級などの評価点をどのように換算するかについてもあわせて検討し、評価の公平さがしっかり担保されるように注意をしましょう。
また、体制として評価期間や頻度も合わせて明確にすることをおすすめします。
評価するまでの期間が長かったり頻度が少なかったりすると、社員の不満に繋がってしまう可能性があります。会社の会計期間やフェーズにあわせて、適切な期間と頻度で評価を実施できるようにしましょう。
4.評価者の選定をおこなう
次に評価者の選定をおこないます。評価者を選定する際は、業務や実績をより理解しているマネジメント層を対象にしましょう。
また、評価者は1名ではなく、部門長、リーダー職など、複数人によって評価するケースが一般的です。評価者が限られてしまうと、普段の仕事ぶりが不透明なまま、誤った評価をしてしまいかねないためです。また、多角的な視点から公平性を保った評価をおこなうためにも、複数人による評価をおこなうといいでしょう。
さらに評価者に対しては、適切な評価やフィードバックの仕方について十分に理解してもらわなければなりません。そのため、評価者に対してはあらかじめ研修を実施しておくことも大切です。
5.評価のフィードバックやレビュー方法を定める
評価結果を社員にフィードバックするための方法や、評価結果の妥当性を検証するレビュー方法についても定めておきます。
フィードバックは、評価の結果を社員に理解してもらい、今後の改善につなげるために必要です。レビューは、評価がきちんとおこなえているのか、その妥当性を検証して評価基準の改善につなげるために必要です。
人事評価を適切に運用したり見える化したりする方法として、ツールの導入も検討できるでしょう。自社の体制に応じたものを取り入れてみるのもいいでしょう。
6.評価結果の振り返りや活用について定める
社員から得られたフィードバックやレビューの評価結果をもとに次期の改善方法を定めていきます。
実施後は得られた情報は必ず全社員との会議や説明会を設けて知らせるようにしましょう。情報を開示しないと、制度自体の改善が社員に伝わらず不満が生じてしまいます。
人事評価の主な評価手法
人事評価制度にはさまざまな評価手法があるため、それぞれの特徴や向いている組織などをここで確認しておきましょう。また、ひとつの評価方法では社員を公平に評価できないケースもあるため、それぞれの手法を併用するのもおすすめです。
MBO(目標管理制度)
MBOは、社員自ら目標を設定し直属の上司が目標達成に向けて活動をサポートしたり、達成の度合いを評価したりする手法です。
社員自身で目標を設定できるため、目標達成に向けた意欲やモチベーションを高めやすい特徴があります。ただし、場合によって高い評価をもらうために目標を低く設定するケースもあるため注意して管理しましょう。
MBOが向いている組織:
- 目標達成を重視したい組織
- 社員の自主性を重視したい組織
OKR評価
OKRは、組織のモチベーションを高めるためにあえて高い目標を設定し、その進捗を図るために具体的な数値を設定する評価手法を言います。
個人の目標に対して成果指標を複数設けることで、目標達成に向けたチャレンジ精神を養えます。MBO評価と比べるとOKRは組織一丸となっても目標達成の意味合いが強い手法です。
OKRが向いている組織:
- 高い目標に向かって挑戦したい組織
- 企業全体の目標と個人目標の連携を重視したい組織
- 目標の明確化と定量的な数値を重視する組織
360度フィードバック
360度フィードバックとは、上司だけでなく同僚や部下、他部署の社員など複数人の視点から評価をする手法です。上司が部下を評価する方法では上司の主観や感情によって左右される場合があり、人事評価のエラーが起きやすい問題がありました。
360度フィードバックでは、立場の異なる社員を評価者とすることで人事評価のエラーを防止でき、公平性や客観性を実現できます。
360度フィードバックが向いている組織:
- 多面的に社員を評価したい組織
- 評価の公平性や納得感を高めたい組織
- 評価者を選定したい組織
コンピテンシー評価
コンピテンシー評価は、企業や組織で高い成果を上げている社員(ハイパフォーマー)に共通する、行動特性に基づいて人事評価をする手法です。
実際に社内で働いている人がモデルになるため、具体的な項目や基準が設定しやすい特徴がります。育成方針の戦略を立てやすい一方で、ハイパフォーマーの選定や分析などには時間や手間がかかります。
コンピテンシー評価が向いている組織:
- 社員の成長やキャリアを支援したい組織
- 目標達成に貢献する社員を評価したい組織
- 客観性や公平性を高めたい組織
内部リンク想定
ID23
人事評価基準を決める際の注意点
人事評価基準は職種や業務内容、企業の成長フェーズによって適切な内容が変化していきます。
そのため、流動的な運営が必要になり、完璧な人事評価を決めるのは難しいです。
それらを念頭において、人事評価基準を策定する際に注意しておきたいポイントについて確認しておきましょう。
評価基準は複数のメンバーやチームで策定する
企業のフェーズや事業目標によって、適用すべき基準は一概には決め難いものです。
複数のメンバーや組織で決めることで、さまざまな視点から評価基準を検討できます。この際に、基本的には経営層や人事を中心に決めるものの、現場社員に近いリーダーなどのマネジメント職も含めて検討することが重要です。
職種ごとに定量目標と定性目標の基準を明確にする
職種によって求められる成果や行動が異なるため、職種ごとに定性的な目標と定量的な目標の基準を明確にする必要があります。
たとえば、営業という職種であれば、ノルマや達成数といった定量的な目標がメインになる一方で、総務や労務などは定性的な目標にコミットしなければならない職種もあります。
どの職種も定量目標が優先されると公平性の維持が難しくなります。各部門の主任や管理者は明確な基準を設けるようにしましょう。
評価者への研修を実施する
人事評価は、評価者の主観によってその基準や結果が左右されてはいけません。
そのため、評価者への研修を実施して評価基準の理解をより深めてもらい、評価に対する公平性の重要性や客観性を高めることが重要です。一度のみならず、一定の年数や評価期間前のタイミングで定期的におこなうなども検討してみるといいでしょう。
定期的に評価基準を見直す
評価基準は一度設定したから終わりではなく、定期的に見直すことでより公平な基準を設定するようにしましょう。
人事評価基準は、運用の過程で改善を重ねることで企業に合ったものになっていきます。
最初の設計段階で、どのように社員の意見を反映させるか、何を持って評価制度の質を判断するかの軸を明確にしておきましょう。
人事評価基準の定期的な見直しにサーベイツール「Geppo」が有効
人事評価への不満は、社員のパフォーマンスやモチベーションの低下に大きな影響を与える可能性があるため、定期的に意見を収集し、見直しと改善に役立てていく必要があります。
「Geppo」は、オンラインで回答できる質問形式の調査をおこない、組織や個人の課題を可視化できるサーベイツールです。
人事評価に対する質問を設定し、集まった意見を分析することで、評価基準の課題を洗い出すことができます。そこから、より社員の声に即した改善策を検討できるため、ぜひ活用してみてください。
まとめ

人事評価制度は、組織の目標達成や人材育成を目的として導入されます。しかし、一度作った制度をそのまま運用し続けると、時代の変化や組織の状況変化に対応できず、課題や改善点が生じる可能性があります。
そのため、ときには評価基準を見直したり、新たに項目を追加したりすることで、より客観的で納得感のある評価制度を構築できます。
さらに評価を受ける社員の意見も取り入れることで、評価基準をよりブラッシュアップできます。その際にはサーベイツールを活用するのも有効な手段であるため、ぜひ検討してみてください。
【監修者プロフィール】

木下 洋平
合同会社ミライオン
株式会社リクルートや教育研修会社での勤務後、現在は独立した専門家として活動。
キャリアコンサルタント資格を取得し、400人以上の個人のキャリア開発をサポート。
また、企業向けの人材育成・組織開発コンサルティングも手掛けており、個人と組織の両面での支援を行っている。