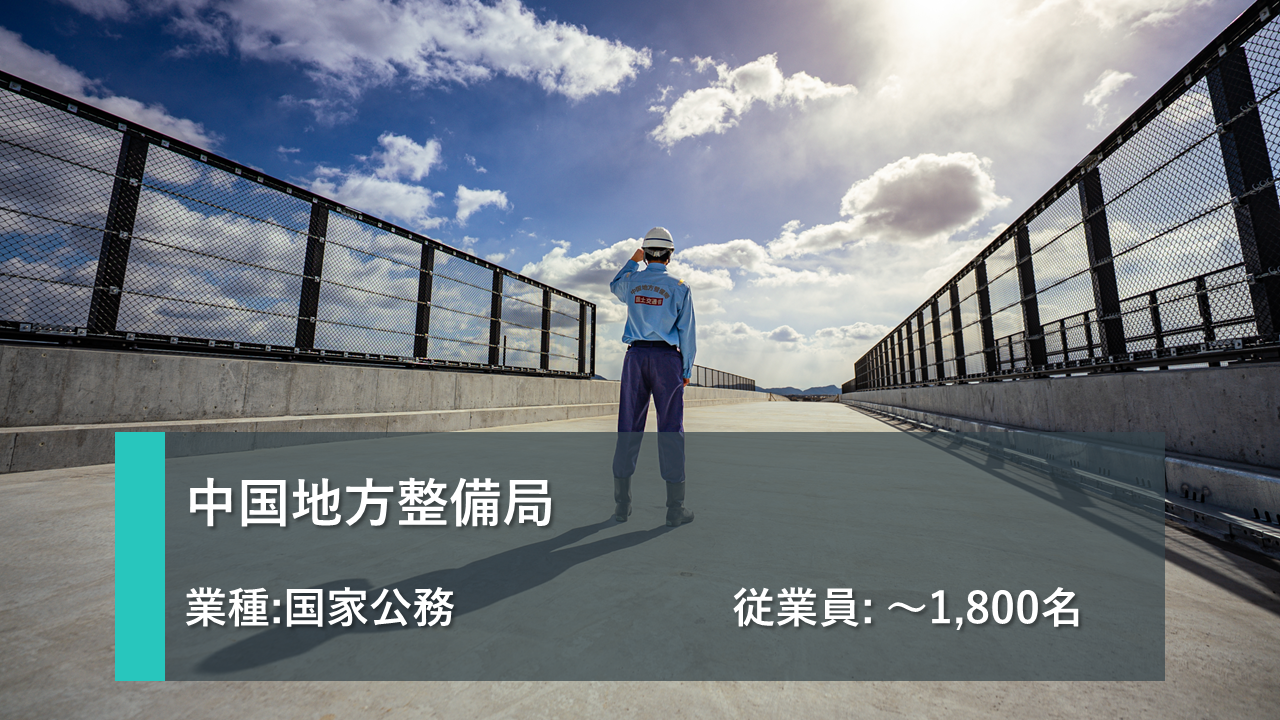エンゲージメントスコアが注目される背景

- エンゲージメントスコアで見ると、決して優秀とはいえない日本
2017年、アメリカの大手調査会社であるギャラップ社が、「Q12(キュー・トゥエルブ)」と呼ばれる12の質問をもとに、全世界139カ国、約1,300万人のビジネスパーソンのエンゲージメント調査を行いました。
この調査における東アジアの「Engaged(エンゲージメントが高い)」といわれる社員の割合は平均6%、日本だけで見ても6%という数値でした。
これはアメリカの31%と比べて大幅に低く、世界平均である15%にも届いておらず、全139カ国の中で132位と非常に低いことが判明しました。
まさにこの調査が、その後日本でエンゲージメントスコアが注目されるきっかけとなったのです。
- 今後を見据え、エンゲージメントスコア向上が喫緊の課題に
おりしも日本では労働人口の減少を迎えており、人材確保が業種・業界を超えた課題となっています。
エンゲージメントスコアが低い状態とは、会社と従業員が良好な関係を維持することができていない状態であり、この状況が続けば、単純な労働力の減少はもちろん、優秀な人材にみすみす離職されてしまうリスクを抱えることになってしまいます。
また、エンゲージメントスコアの改善によって社員の主体性が養われ、業務改善なども積極的に実践された場合には、生産性向上が期待できるという点も見逃せません。
日本はかつて、企業と従業員が強固な主従関係にありました。
会社は従業員の生活を保障するかわりに、従業員は労働力を提供する、という関係性ができあがっており、その弊害として、企業に従業員が過度に依存してしまい、自分で判断して行動ことができない、もしくは自分で判断することを嫌う「ぶら下がり社員」というものを生み出していました。
そして、従業員を長時間働かせる労働環境にも批判が高まっていました。
エンゲージメントの向上によって成功体験や労働時間の削減などがもたらされることは、働き方改革を迎えた日本にとっては非常に歓迎されるべきことで、新たな指標として、エンゲージメントへの期待が高まっていきました。
エンゲージメントが高まり、結果として生産性が向上し、業績が良くなり、それがさらなるエンゲージメント向上につながるという、ポジティブな循環を作ることは、限られた人材でより良い会社経営を行っていくために重要なことなのです。
エンゲージメントスコアが高い企業の特徴とは?

それでは、エンゲージメントが高い企業とはどのような企業なのでしょうか?
エンゲージメントは、企業やそこで働く従業員によっても変わってくるものであり、「これができていればエンゲージメントが高い!」と断言することは難しいもの。
しかし、ある程度の傾向はわかってきています。
ここでは、エンゲージメントが高い企業がもつ傾向についてご紹介します。
- 風通しが良く、心理的安全性に優れている
風通しがいいというのは、要するに会社での立場に関係なく「言いにくいことや本音が言える」ということ。
たとえばミーティングでも「上司にはめったなことは言えない」という雰囲気が張り詰めているのではなくて、「まずはなんでも言ってみよう」と思えるフランクな雰囲気があることなどが当てはまります。
これは専門用語で「心理的安全性」といわれるもので、つまりは「相手に関してリスクのあることが言える」という状態のことを表します。
もっといえば心理的安全性は「多様なメンバーが尊重しあい、共に考え、意見が遠慮なく言える」ということなのですが、それは決して身内に甘いという状態ではなく、日々なんとなく業務をこなしていれば、安定して給与が上がっていく、というぬるま湯のような環境とも異なります。
むしろ、率先して自分の意見を話したり、立場が上の人間に対しても積極的に反論したりすることが奨励されるような、特に上の立場の人によっては、より厳しい環境といえるかもしれません。
他にも、当たり前のように扱われている内容に対して「これってそもそも必要ですか」という「そもそも論」が出てくることもあるでしょう。
つまり、業務環境や効率を上げるために、対等な立場から意見をぶつけあえる環境のことを指します。
一見すれば意見が衝突しあうギスギスした状態に映るかもしれませんが、これが「健全な衝突をしている」状態であり、心理的安全性が高いということ。
要するに、「発言で無知をさらしたくない」「意見が邪魔だと感じられたら困る」という不安を感じかねない状況でも「この人なら、このチームなら言っても大丈夫だ」と思えるのが心理的安全性なのです。
この心理的安全性こそ、エンゲージメントを高めるために重要な指標だと考えます。
- チームワークが良い状態にある
風通しの良さとも関連しますが、エンゲージメントを高めるためにはチームワークも非常に大事な要素です。
チームワークが良い状態というのは、みんなの意見が一致する、ということではなく、共通の目標達成に向けて、お互いにフォローしあい、間違いを指摘しあえるようなお互いを高めていける関係のことを指します。
- 個性を活かしてチーム全体のパフォーマンスを高めている
適材適所でチームのパフォーマンスを上げるには、メンバーそれぞれの個性を活かそうとする感覚が欠かせません。
日本企業では、これまで総合職やゼネラリストと呼ばれるオールマイティーな人材を育ててきた傾向があります。
これは労働人口がまだ多かった頃、さまざまな仕事をある程度の水準でこなすことができる人材が重宝されていたという時代背景があったからです。
しかし、労働力が不足している昨今では、むしろ特定の分野に強みを発揮するスペシャリストが求められる傾向にあります。
社会的な背景を抜きにしても、誰でもできる業務を行うことよりも、自分が活躍できる分野で会社に求められて業務を行うことの方が、満足度が高くなる傾向にあります。
従業員一人ひとりの特性を理解し、強みのある分野で活躍してもらい、弱い部分は、それが得意な人がカバーする。
こうした相互にカバーしあえる環境がエンゲージメントを高めるためには重要です。
総合職として、会社都合で一方的に配属が決められてしまう会社よりも、キャリアパスが選べる企業は、総じてエンゲージメントスコアが高くなっていると感じます。
- チャレンジしようとする企業風土がある
新しいことにあまり怖気づかず、「とにかくやってみよう」とGOサインを出したり、失敗しにくい手堅い方策でなくても、将来性が感じられれば「いいね」と評価する。
こういった企業風土をもっていることも、やはりエンゲージメントが高い企業の特徴といえます。
逆にいえば、「会社は(上司は)冒険をしようとしない、新しいことを取り入れたがらない」というあきらめが生まれるような企業風土や、失敗した時の責任を部下に押し付けてしまうような企業風土では、社員の仕事のやりがいを奪い、エンゲージメントを下げてしまいます。
エンゲージメントスコアは、企業と従業員の関係性をわかりやすく可視化するために大切な指標です。
エンゲージメントスコアが高い企業の特長としてはさまざまなものがありますが、共通している点としては、企業が従業員の目線に立って環境を構築できている、という点があります。
従業員の声に耳を傾け、やりがいと快適な労働環境を提供することに注力すれば、エンゲージメントスコアは高まり、結果的にはそれが企業の業績アップへとつながっていきます。
また、こうした評判が広まれば、新たな人材とも縁が結ばれていくかもしれません。
ポジティブな循環を自社にもたらすためにも、従業員の声を集められるアンケートなどは定期的に行っていくようにしましょう。
そこで得られた結果を受け止め、それぞれの企業、従業員に合った対策をとることがエンゲージメントを高める最良の策となるでしょう。
【監修者プロフィール】

森田 英一
beyond globalグループ(シンガポール、タイ、日本)
President & CEO
大阪大学大学院 卒業。外資系経営コンサルティング会社アクセンチュア(当時、アンダーセンコンサルティング)にて人・組織のコンサルティングに従事。2000年にシェイク社を創業し、代表取締役社長に就任。主体性を引き出す研修や、部下のリーダーシップを引き出す管理職研修や組織開発のファシリテーションに定評がある。現在は、beyond globalグループのPresident & CEOとして、エンゲージメント向上プロジェクト、企業文化変革、経営者育成、組織開発、次世代リーダー育成、HRテック導入支援、各種プロジェクトを行っている。主な著作「3年目社員が辞める会社 辞めない会社」(東洋経済新報社)「一流になれるリーダー術」(明日香出版)「会社を変える組織開発」(php新書)等。日経スペシャル「ガイアの夜明け」 「とくダネ!」 等メディア出演多数。