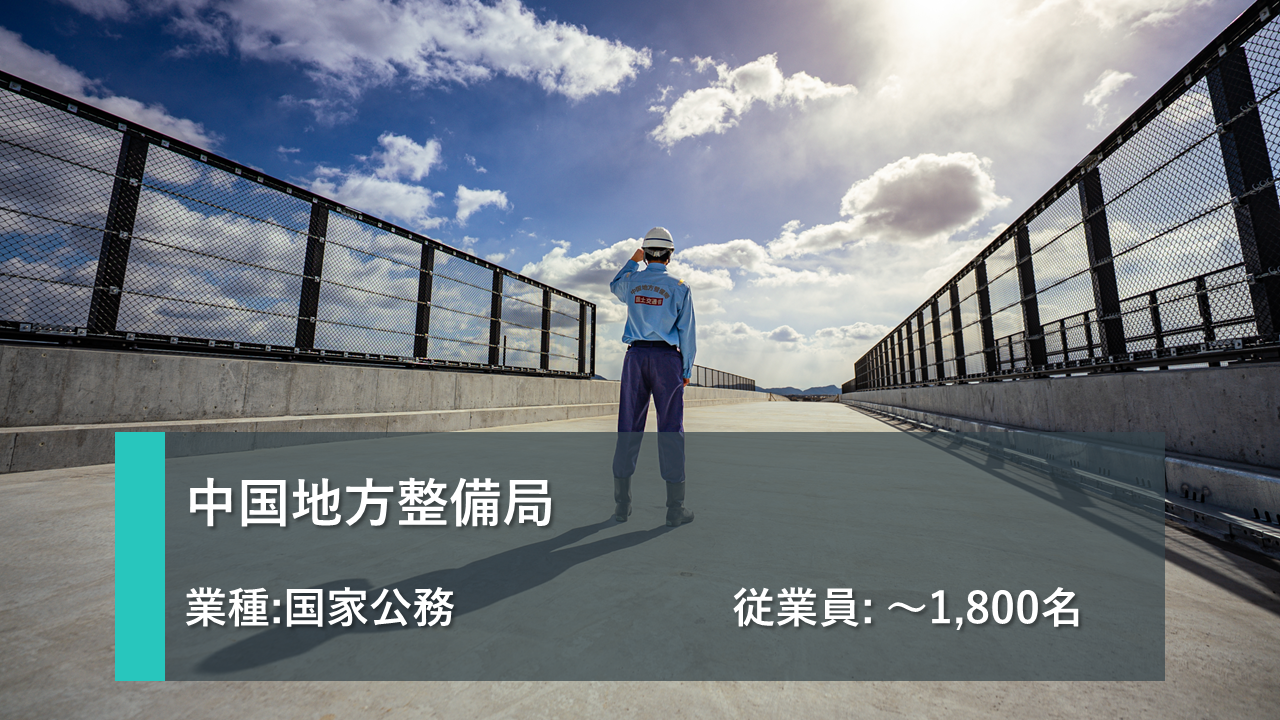エンゲージメントサーベイツールはたくさんあってどれを選んだら良いかわからない……という方も多いのではないでしょうか。
今回は専門家監修のもと、ツールの選び方のノウハウをご紹介いたします。
自社の状況と照らし合わせ、必要なものを取り入れていきましょう。
エンゲージメントサーベイとは?

- エンゲージメントサーベイとは「前向きな貢献意欲を可視化する調査」
・エンゲージメントサーベイは「組織サーベイ」の一種
「従業員と組織・仕事の関係性を測る」調査にはさまざまなものがあり、それらを総称して「組織サーベイ」と呼ぶのが一般的です。
これらの調査はその目的や実施方法などによって本記事のテーマであるエンゲージメントサーベイをはじめ、モラールサーベイ、従業員満足度調査などに分けられますが、互いに共通する部分も多く、厳密には区別できない側面もあります。
・具体的には「前向きな貢献意欲を可視化する」ための調査
「サーベイ」は「測定」「調査」といった意味で、つまり「エンゲージメントサーベイ」はエンゲージメントを測定する調査を指します。
「エンゲージメント調査」と呼ばれることもあります。
では「エンゲージメント」とは何かというと、人材マネジメント分野においては、従業員の「組織(会社)や仕事に対する前向きな貢献意欲」のことを示します。
やる気もなく、前向きでない姿勢で仕事をする社員ばかりの会社はパフォーマンスが上がりません。
そこで、まずは社員が会社に対してや自分の仕事に対してどれだけ前向きに成果を出そうと考えて取り組んでいるかという度合いを測ろうという調査がエンゲージメントサーベイなのです。
他のサーベイとエンゲージメントサーベイの違いとは?

エンゲージメントサーベイと「目的が違う」サーベイ
人材マネジメントにおけるサーベイは、調査の目的によってエンゲージメントサーベイをはじめとするいくつかの種類に分かれます。
いずれのサーベイも調査結果は個人レベルではなく、統計分析による「組織全体のスコア」として現れます。
では、それぞれを見ていきましょう。
(1)モラールサーベイ
従業員の調査を通じて「組織全体の士気、いわゆるやる気や意欲」を測る調査です。
従業員が「自分の置かれた労働環境にどのような感情や認識を持っているか」を数値化するところまではエンゲージメントサーベイと似ていますが、エンゲージメントサーベイが『「(組織で働く)個人」の組織や仕事に対する前向きな情熱がどの程度なのか』を数値化するのに対して、モラールサーベイでは『「(個人の集合体としての)組織全体」の士気がどの程度なのか』を数値化します。
似ている言葉に道徳や倫理という意味を持つ「モラル」がありますが、これらはまったく異なる概念です。
(2)従業員満足度調査(ES調査)
従業員の調査を通じて「組織全体の労働環境や待遇などへの満足度」を測る調査です。
給与や福利厚生といった項目だけではなく、会社の理念、方針、戦略や上司の職責遂行度なども調査対象になりますから、調査の設問などはやはりエンゲージメントサーベイやモラールサーベイと似てきます。
ただし従業員満足度調査ではやる気や士気ではなく、「会社から与えられている現状にどの程度満足しているか」を数値化します。
(3)ストレスチェック
従業員の調査を通じて「組織全体の健康状態などのストレスレベル」を測る調査です。
「ストレス」とは、外部から刺激を受けた時に起こる緊張状態のこと。
「労働環境に限らず、身体的な要因や個人的な悩みで起こっているストレスも含めて、どのような状況にあるか」を数値化します。
エンゲージメントサーベイを含めたいずれの調査も、第三者が管理していなければ、社内への結果流出への懸念から、回答内容に影響が出る可能性があります。
つまり、匿名で自由に回答できる状況が好まれます。
- エンゲージメントサーベイと「調査頻度が違う」サーベイ
・エンゲージメントサーベイは「センサス」の一種
エンゲージメントサーベイの主な実施方法は、従業員へのアンケート調査です。
実施の頻度は半年~1年ごと、設問も細かいことより総合的な内容が中心で、数十問にわたるというのが一般的です。
こうした調査方法のサーベイは、「センサス」とも呼ばれます。
エンゲージメントサーベイも、センサスの一種として数えられることがあります。
全数調査を意味しますので、国勢調査などもセンサスの一つです。
・センサスとは調査頻度が違う「パルスサーベイ」
センサスとは異なり、月次、週次などの短いスパンで、脈拍(パルス)を取るように従業員の日ごとの状況を見る調査を「パルスサーベイ」といいます。
パルスサーベイは調査手法を指す言葉なので、何を測定するかはその調査の目的によりますが、たとえばパルスサーベイでストレス状態を調べ、結果の推移を分析することで、ストレスの原因を突き止めるといった活用法があります。
パルスサーベイは特性として「組織の中の個人の状況や、それにかかわる課題を見つける」ことを得意としています。
つまり、記名など回答者を特定できる状態で実施することが望ましいのです。
・どちらを選ぶか、ポイントの一つは「社員数」
センサスには「組織全体のスコアを出す」という特性から、ある程度の回答数、つまり社員数が求められます。
具体的に挙げると、少なくとも社員数100~200人程度であれば、会社全体の傾向は分析できます。
しかしこの場合も、部門や部署といったより小さい単位になると、統計学的に必要なサンプル数が足りず、有意といえる分析結果が出せない可能性が高いです。
社員数100人を下回る中小企業の場合は、会社全体の傾向を出すのも難しいかもしれません。
一方、社員数が少ない企業でも、「組織の中の個人の状況や、それにかかわる課題を見つける」特性を持つパルスサーベイなら、業務改善に活用できます。
※組織サーベイについては、下記記事でも詳しく紹介しているのでぜひご参考ください。
エンゲージメントサーベイの実施方法は?

- 自社でアンケートを作成する
・融通が利くが、専門家を入れなければ改善につながりにくい
エンゲージメントサーベイの実施方法の一つに「自社でオリジナルのアンケートを作成し、Webフォームやアンケート用紙などを用いて調査する」ものがあります。
自社で自由に設問設計ができますし、現業職などでPCの個別支給がない部署がある場合には、紙のアンケートで回答してもらうといった融通が利きます。
ただし、エンゲージメントサーベイで「組織全体のスコアを出す」には、専門性の高い統計分析が欠かせません。
自由に設問設計ができるとはいえ、専門家の監修のもとで設計しなければ、課題に関する仮説を立ててその検証を行う……といった重要なポイントが成り立たず、「集計結果を見て終わり」になる可能性が高いのです。
もちろん、現状把握や改善への効果期待が弱くなります。
- 外部ツールを導入する
・ツールの選び方次第でかなり有効な打ち手になる
エンゲージメントサーベイの実施方法にはもう一つ「外部ベンダーが提供しているエンゲージメントサーベイツールを導入し、Web上の専用ツールを用いて調査する」ものがあります。
Web上で調査を実施しやすいのはもちろん、多機能・高性能なツールも多く、選び方や運用方法次第でかなりコストパフォーマンスを上げられる方法です。
もちろん、こちらも自社でアンケートを作成する場合と同様に、エンゲージメントの様子を知るための効果的な設問をしっかりと考える必要があります。
ただし、その際にサポートがあり、ツール自体の機能を活用できたり、ベンダーのスタッフからアドバイスを受けたり、といったメリットもツールによっては期待できます。
エンゲージメントサーベイツールを選ぶ前に

- エンゲージメントサーベイの目的をしっかり意識して
・使いやすくても「欲しい成果物が手に入らない」のでは意味がない
エンゲージメントサーベイツールに限らず、ITソリューションを選ぶ際にはつい「使いやすさ」や「わかりやすさ」などの部分に注目しがちです。
確かに、快適に扱えることは重要なポイントの一つではありますが、いくら使いやすいツールでも「そのツールにできること」と「自社がそのツールに求めているもの」が違えば、導入した意味がなくなってしまいます。
エンゲージメントサーベイツールでたとえると、「操作が簡単な一方、見られるのは集計結果だけ」というツールと、「操作に慣れるまでは少々大変だけれど、簡易分析や調査結果の推移なども詳しく見られる」のではまったく違います。
もちろん「後者が良いからがんばって操作に慣れよう」という話ではなく、そもそも集計結果だけを見たいのであれば、前者の「操作が簡単なツール」の方が自社に合っている……つまり「求めているもの」を見極めることが重要なのです。
・まずは「自社が求めているもの」を明確に
そこで、ツール選定にあたってはまず「自社がエンゲージメントサーベイに求めているもの」を明確にしてから臨みましょう。
エンゲージメントに関する現状をわかりやすく把握できればそれで良いのか、そこから踏み込んで課題やその原因に迫り、改善を図りたいのか、自社にはどれくらいツールを扱える人員がいるのか、外部の専門家の手を借りた方が良いのか、もちろんどれだけ予算をかけられるかも重要です。
買い物にたとえるなら「いきなり売り場へ行くと、雰囲気に流されて目的に合わないものを買ってしまったり、必要ないものまで買ってしまったりするかもしれない」ということです。
この場合、事前に何を買うか検討して、買い物メモを作っておけば安心ですよね。
ツール導入に関してもこうした計画性を持つことが、失敗を遠ざけるだけでなく、あらかじめツールへの理解を深め、導入後にしっかり使いこなすことにもつながります。
エンゲージメントサーベイツールの選び方のヒント
- ある程度候補を絞ってから「どこを見るか」
こうして「自社がエンゲージメントサーベイに求めているもの」をはっきりさせておけば、数あるエンゲージメントサーベイツールの中でも、導入するべきツールはある程度絞れてくるのではないでしょうか。
最後に「絞られた候補の中から、自社にとって役立つツールを選ぶ」ためのちょっとしたヒントを紹介します。
(1)体験版は複数試して比較検討を
体験版のあるツールは、ぜひ使ってみましょう。
導入するツールはもう決まっていて、契約前に試してみるだけ……ということもあるかもしれませんが、できればそれよりも前に、複数のツールを試してそれぞれ比較することをおすすめします。
比べてみることで、思わぬポイントに気づくかもしれません。
(2)FAQページをチェックしてみる
「新しいツールを入れたいけれど、わからないことがあった時のサポートがしっかりしているか不安」と考える方は多いものです。
そんな時は、ツールのFAQページをチェックしてみましょう。
ページデザインや項目がユーザー目線で考えられているか、説明の文章はわかりやすいか、内容に沿ったリンクが貼られているかといったポイントから、そのベンダーのサポート体制も見えてきます。
(3)導入事例は「自社に近い」ものを参考に
ベンダーや代理店が提供している導入事例記事は、現場で実際にツールが活用されている様子がわかるとても良い情報源の一つです。
ただし自社とはまったく規模が違う企業の、大がかりなプロジェクトに感動して、そのツールを自社へ導入しようとしたり、まるで社風が違う企業の導入前後のフローを、無理やり自社でも真似したりするのは考えもの。
記事を読んで検討するのは良いことですが、実際に参考にする事例は会社規模などが近いものにしておきましょう。
(4)シェアNo.1が自社に合うとは限らない
多くの企業が使っているツールや、口コミの内容が良いツールはそれだけで魅力的に見えるものですが、人気のツールが必ずしも自社の目的に合うとは限りません。
自社にとって「良いツール」は、自社やその目的との相性も含めたものだということを意識して、新進のツールや、ユーザー数があまり多くないツールにも目を向けてみましょう。
もちろん「不人気な方が面白い」というわけではなく、人気のツールが自社にも合っているならそれで良いのです。
エンゲージメントサーベイツールの選び方は、導入する企業や目的とするものによって千差万別です。
これと決まった正解があるわけではありませんから、まずは自社がエンゲージメントサーベイに何を求めるのかを検討し、明確にするところから始めましょう。
そうすると「エンゲージメントサーベイツールはどれが良くて、どれがダメなのか?」という曖昧かつ恣意的な選び方ではなく、「自社に合うエンゲージメントサーベイツールはどれか」といった、より論理的な選び方が見えてくるはずです。
【監修者プロフィール】

吉田 寿
HRガバナンス・リーダーズ株式会社
指名・人財ガバナンス部 フェロー
BCS認定プロフェッショナルビジネスコーチ
早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了。
富士通人事部門、三菱UFJリサーチ&コンサルティング・プリンシパル、ビジネスコーチ常務取締役チーフHRビジネスオフィサーを経て、2020年10月より現職。
“人”を基軸とした企業変革の視点から、人財マネジメント・システムの再構築や人事制度の抜本的改革などの組織・人財戦略コンサルティングを展開。
中央大学大学院戦略経営研究科客員教授(2008年~2019年)。
早稲田大学トランスナショナルHRM研究所招聘研究員。
主要著書『働き方ネクストへの人事再革新』(日本経済新聞出版)等多数。