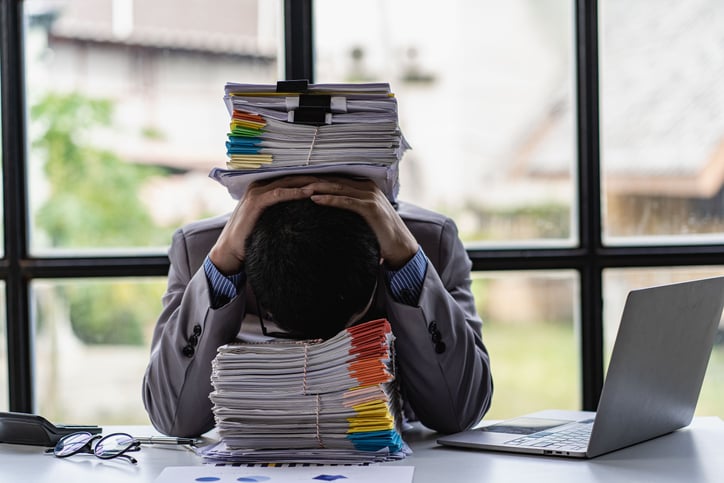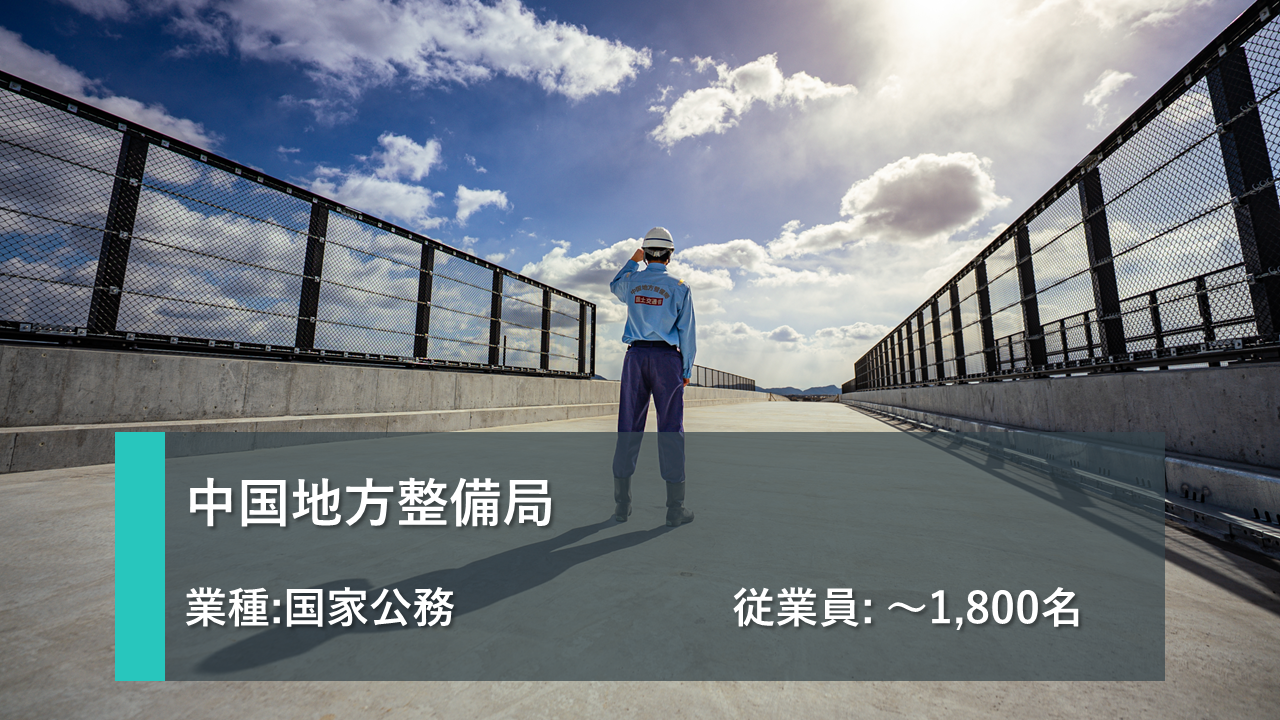職場におけるパワハラ被害を防ぐため、2020年6月に大企業を対象として施行された「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」。
2022年4月からは中小企業もその対象となり、すべての企業にパワハラ防止対策が義務付けられることとなります。
今回は、この法律の概要とともに、企業に求められる対策の具体例や、訴訟が起こった際に取るべき対応についてご紹介いたします。
「パワハラ防止法」とは?

- 改正労働施策総合推進法=パワハラ防止法
「パワハラ防止法」という名称は、「労働施策総合推進法」を改正する際に付けられた通称です。
労働施策総合推進法は、労働環境の改善や多様な働き方の推進を目的として、2018年に制定されました。
その際に、職場におけるパワーハラスメント防止の規定が盛り込まれたことから、「パワハラ防止法」と呼ばれるようになりました。
改正の背景にあったのは、職場におけるパワハラの社会問題化です。
厚生労働省の調査※によると、総合労働相談コーナーに寄せられる職場でのハラスメントについての相談件数は、年々増加。
10年前と比べると2倍以上の数になっており、問題の深刻化が指摘されてきました。
こうした状況を踏まえ、2019年5月に労働施策総合推進法が改正され、2020年6月に施行。
大企業については2020年6月から、中小企業については努力期間を経て2022年4月から、パワハラ防止対策が義務付けられることとなりました。
- パワハラ防止法におけるパワハラの基準とは?
パワハラ防止法の成立に伴い、パワハラに関する明確な判断基準が設けられることとなりました。
(1)パワハラの基準となる3要素
具体的には、次の3つの要素をすべて満たす言動がパワハラに該当します。
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③就業環境が害されるもの
参照:
(2)パワハラ行動の6類型
また、パワハラになり得る具体的な行為としては、以下の6つの類型があります。
ただし、個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ることや下記が限定列挙ではない(ここに記載されていないものはパワハラに該当しないということではない)ということには留意が必要です。
①身体的な攻撃(殴打や足蹴り、物を投げつけるなど)
②精神的な攻撃(人格を否定するような言動、必要以上の叱責など)
③人間関係の切り離し(無視や仲間外れ、隔離など)
④過大な要求(遂行不可能なことの強制、私的な雑用の押し付けなど)
⑤過小な要求(嫌がらせのために容易な仕事を命じる、仕事を与えないなど)
⑥個の侵害(職場外での監視、本人の了解がないままの個人情報の暴露など)
パワハラ防止法で企業に課せられる義務

- パワハラ対策4つの義務
パワハラを防止するために企業の義務となるのは、以下の4つの措置です。
(1)事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
パワハラに対する企業としての方針を明確にし、規則を整備して、従業員に知ってもらう必要があります。
どのような行為がパワハラとなるのか、また、パワハラを行った場合にはどのような対処をすることになるのか。
こうした点を就業規則や社内報に明示するとともに、研修を行うなどして従業員の理解を深める必要があります。
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
従業員のパワハラ相談のために制度や窓口を設けることが求められます。
相談窓口においては被害者が委縮する例もあることを踏まえて、適切な対応をする必要があります。
(3)職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
パワハラの相談があった際には、事実関係を正確かつ迅速に確認しなければなりません。
事実確認において、相談者と行為者の主張が食い違う場合は、状況に応じて第三者へのヒアリングなどが必要になることもあります。
また、相談者のメンタル不調などに対して適切なケアやサポートを行うと同時に、行為者へのケアも必要です。
パワハラの事実が確認された場合、規定に沿った対処を行うとともにカウンセリングを通して意識改革を行うなどし、パワハラの再発防止に努めなければなりません。
(4)併せて講ずべき措置
(1)~(3)の措置と併せて、相談者や行為者のプライバシーを保護することも求められます。
相談や事実確認の際に協力をした従業員が、不当な扱いを受けたり不利益を被ったりしないよう配慮しなければなりません。
パワハラ防止法では、これらの措置を企業が怠った場合の直接的な罰則までは設けられていません。
しかし、厚生労働省による指導や勧告の対象となる可能性があり、勧告に従わない場合には公表されることもあるため十分な注意が必要です。
知っている?パワハラは「労災認定」される!

- 精神障害の労災認定基準にパワーハラスメントの項目を追加
労災とは「労働災害」の略で、労働者が勤務中や通勤中に負う怪我や病気、障害などを指す言葉です。
労災が発生した場合、事業主が保険料を負担する労災保険から被害者に対して、給付金が支払われます。
厚生労働省では、 パワハラ防止法の施行に合わせて、労災の認定に関わる「心理的負荷による精神障害の認定基準」についても改正を行っています。
これにより、労災認定の際に用いられる「業務による心理的負荷評価表」に「パワーハラスメント」の項目が追加。
パワハラ被害が労災補償の対象として明確になりました。
- パワハラに適用される労災認定基準とは?
パワハラの被害が労災として認められ、労災保険を受給するためには以下の3つの認定要件をすべて満たしている必要があります。
①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
②発病前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
参照:
ここで言う「心理的負荷」とは、精神的な苦痛やストレスのことを指しています。
実際の認定判断は、「職場における心理的負荷評価表」と「職場以外の心理的負荷評価表」をもとに、労働基準監督署が行います。
労災は会社の過失の有無に関わらず、業務上の理由で労働者が負傷・疾病となった際に支給されるものですが、パワハラを原因としたメンタルヘルス不調などにより労災が認められた場合、会社の安全配慮義務違反として、会社に損害賠償請求をされる可能性もあります。
パワハラで訴訟が起こったら?企業が追う責任とは

- 企業には3つの責任がある
パワハラが発生した場合、パワハラをした行為者はもちろん、行為者を雇用している企業も責任を問われる可能性があります。
訴訟が起こったら、企業は以下の3つの責任を負うことになります。
(1)パワハラ行為者の処分を行う責任
会社は、パワハラの行為者に対して処分を行う必要があります。
具体的な処分の内容は、行為者の言動の悪質性や被害者にもたらされた影響の大きさなどを考慮して検討します。
たとえば、暴行や脅迫、名誉棄損などが行われていた犯罪行為レベルのパワハラの場合、出勤停止や降格、懲戒解雇といった処分を検討することになります。
また、嫌がらせ目的の強い叱責に起因して被害者が精神障害を発症するなど、民法上の不法行為レベルのパワハラの場合は、降格や出勤停止などの処分が相当とされるケースが多くなります。
そして、無視をしたり悪口を言ったりといった職務遂行を阻害するような職場環境レベルのパワハラの場合、戒告や減給などの処分が検討されます。
注意や指導を与えたうえで是正されない場合にのみ、懲戒処分となることもあります。
行為者が管理職などの立場にある場合は、職務適性がないと見なされ、パワハラの程度や回数により、降格や解雇となるケースもあります。
(2)使用者責任
会社には、使用者責任があります。
これは、雇用している労働者が第三者に損害を与えた場合、会社がその責任を負うというもの。
これは、会社は労働者の行為によって利益を得ているため、労働者が行為をするうえで生じた損失については会社が責任を取るべきだという考えに基づいています。
労働者のパワハラに対してももちろん、会社はその使用者として責任を負うことになります。
会社がやるべきことをやっていた(相当の注意を払っていた)という場合は、会社の責任の程度が低くなったり、免責されることもありますが、パワハラの事実があり、争いになるような場合、会社にまったく過失がないと認められることはなかなか難しいところです。
(3)安全配慮義務
安全配慮義務とは、その名の通り「従業員が安全と健康を確保しながら働けるよう配慮すること」。
安全配慮義務違反となるかどうかは、「予見可能性(危険な事態や被害の可能性を事前に予見できたかどうか)」と「結果回避性(予見できた損害を回避できたかどうか」の二点を鑑みて判断されます。
この安全配慮義務は、労働契約に伴うものです。
安全配慮義務違反があり、労働者が負傷したり病気になったりした場合は、会社が労働契約を果たしていないということになりますので、債務不履行や不法行為による損害賠償請求を受ける可能性があります。
厚生労働省「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(3)民事上の個別労働紛争|主な相談内容別の件数推移(10年間)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000643973.pdf
【監修者プロフィール】

山本喜一
社会保険労務士法人日本人事 代表
特定社会保険労務士
精神保健福祉士
大学院修了後、経済産業省所管の財団法人で、技術職として勤務、産業技術総合研究所との共同研究にも携わる。その後、法務部門の業務や労働組合役員も経験。退職後、社会保険労務士法人日本人事を設立。社外取締役として上場も経験。上場支援、メンタルヘルス不調者、問題社員対応などを得意とする。
著書に『補訂版 労務管理の原則と例外-働き方改革関連法対応-』(新日本法規)、『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『企業のうつ病対策ハンドブック』(信山社)。他、メディアでの執筆多数。